Magazine
Quantsマガジン
プロジェクトが遅延する原因8選!遅れる理由とその防止策・リカバリ方法を解説!
プロジェクト遅延とは、プロジェクトの進捗が予定通りに進まない事象を指します。何らかの原因によりプロジェクト遅延が発生した場合、顧客と自社に深刻なダメージを与える恐れがあります。遅延の原因と防止策を把握し、事態をコントロールしましょう。
プロジェクトの遅延とは
プロジェクト遅延とは、プロジェクトの進捗が予定通りに進まない事象を指します。プロジェクト遅延により納期が遅れ、顧客の損害や自社の信用失墜、機会の損失等の被害を受けるおそれがあります。プロジェクト遅延が発生する際、予兆が現れるケースがほとんどです。
その予兆を見逃さず、適切な対策を取れば遅れを防止できます。ここではプロジェクト遅延を防止するために、遅れの原因とリカバリの方法、防止策を紹介します。
プロジェクトとは
プロジェクトとは特定の目標を達成するために行われる、目標設定、計画、編成、実行、監査、完了といった一連の活動です。プロジェクトはQCD(Quality:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)を達成目標の指針とし、プロジェクトが達成したかを判定します。
プロジェクトは、自社の発展に重要な役割を持ち、プロジェクトを成功させることで自社の競争力強化や収益向上に貢献できます。
プロジェクトマネージャー(PM)とは
プロジェクトマネージャー(PM)とは、プロジェクトの責任者です。プロジェクトマネージャーの役割は多岐にわたり、計画の立案、プロジェクトチームの編成、ステークホルダーとの交渉、プロジェクト全体の進捗管理等のプロジェクトを成功させるための活動全般を担います。プロジェクトマネージャーには専用の資格(PMP資格やプロジェクトマネージャー試験)があり、難易度の高い役割です。
プロジェクトが遅延する原因8選とその理由
プロジェクトには必ず何らかのリスクが存在します。すべてのリスクを事前に把握することは非常に困難です。そのため、プロジェクトは何らかの問題が発生し、遅延が発生する前提で推進する必要があります。プロジェクト遅延の原因を把握することは、今後のプロジェクトを円滑に進める上で重要です。
ここではプロジェクト遅延の原因を紹介します。
遅延原因1:外注管理の不備
プロジェクト遅延の原因として、外注先管理の不備があります。プロジェクトではタスクの一部を外注するケースもあるでしょう。その外注先からの納品が遅延したり、品質が基準を満たさずに差し戻しとなり、結果遅延となったりする場合が該当します。この場合、外注先の問題点に前もって気付かないと対策できません。
また、遅れを確認した時点で既に手遅れの場合もあります。これは、外注先との情報共有や進捗状況管理を適切に実施していない場合に多く発生します。
理由:外注先からの報告の遅れ
外注管理の不備になる理由として、外注先からの報告の遅れが挙げられます。外注先に発注した作業が、人員不足やスキル不足で完成しない場合に、外注先が自分で何とかしようとして報告しない場合が該当します。
対策としては、外注先を選定する際に何度か取引があり問題ない外注先や、確実に完成可能な信頼できる外注先に発注を絞る方法が有効です。また、外注先との定期的な進捗報告を義務付けたり、外注先を訪問し現状を監査したりする方法も効果があります。
遅延原因2:進捗管理の不備
プロジェクト遅延の原因として、進捗管理の不備があります。プロジェクトの成否を握るのは、進捗管理といっても過言ではありません。プロジェクトはさまざまな要員がそれぞれ別のタスクに従事します。要員によっては他のプロジェクトと兼任している場合もあるでしょう。
プロジェクトを兼任している要員が他プロジェクトの遅延により、自プロジェクトに参加できなくなるおそれがあります。この場合、進捗を密に監視していなければ、迅速に遅延の兆候を発見できません。特に成果物に依存関係がある場合、1つの遅れが他のタスクの遅延も招きます。そのため、プロジェクトの進捗管理は極めて重要です。
理由1:メンバーの進捗報告不備
進捗管理の不備の理由として、メンバーの進捗報告不備が挙げられます。プロジェクトに参画するメンバーはスキルも経歴もさまざまです。人員不足のため、スキルが不足している要員をアサインすることもあるでしょう。問題が発生し遅れているメンバーが、進捗遅れを自分で何とかしようとして隠す場合もあります。
対策としては、チームメンバーが問題や遅延を報告しやすい雰囲気を醸成したり、ガントチャートなどの管理ツールを利用して、進捗を可視化したりする方法が有効です。特に報告しやすい雰囲気を醸成すると、チーム内の結束が強くなり問題に一丸となって対応する等の効果も期待できます。
理由2:PMからステークホルダーへの報告不備
進捗管理の不備の理由として、PMからステークホルダーへの報告不備が挙げられます。プロジェクトマネージャーはプロジェクト全体の管理を行いますが、プロジェクトに問題が発生し遅延になった際に、ステークホルダーへ報告せず隠す場合があります。
プロジェクトに問題が発生した場合、プロジェクトマネージャーはまず上長となるステークホルダーへ必ず報告しなければなりません。その上で、問題を分析し対策を立て、進捗を正常に戻すことが最優先となります。対策としては、定期的な進捗報告会やミーティングを開催する方法が有効です。
遅延原因3:スケジュール不備
プロジェクト遅延の原因として、スケジュールの不備が挙げられます。プロジェクトを開始する際に、タスクを抽出してスケジュールを作成しなければなりません。計画当初の段階で、タスクの抽出漏れやリスクの想定不足などが生じると、スケジュール作成当初から必要な工程が不足し、プロジェクトの遅れの原因となります。
また、大規模プロジェクトの場合は、当初の微細な漏れが、工期の後半になるにつれて大きな遅延につながります。
理由1:前提条件が不明瞭
スケジュール不備になる理由として、前提条件が不明瞭なケースが挙げられます。例えばシステムを構築するときに、新技術を使うのか、既存の技術を使うのか、何の言語を利用するか、利用する言語のライブラリが整っているかによって大きくスケジュールが変わります。
スケジュール不備の理由として、前提条件の明確さは非常に重要です。対策としては、前提条件を明確にするしかありません。有識者を集めて、不明瞭な点や考えられるリスクをレビューする方法が有効な対策です。
理由2:作業項目の割り出し不備
スケジュール不備になる理由として、作業項目の割り出し不備が挙げられます。プロジェクトは開始時に抽出したタスクに基づいて、工数を積み上げて算出します。タスクの抽出漏れがあると、それだけで工数が不足し必要な人員を集められません。
気づいた時点で追加分の作業項目を洗い出し、スケジュールや工数を追加することは可能ですが、当初計画の変更となり、ステークホルダーの承認が必要になります。そのため、最初の計画が非常に重要です。
対策としては、スケジュール作成時にPMOや有識者とレビューして、作業項目の割り出し不備がないかをチェックする方法があります。
理由3:策定者の力量不足
スケジュール不備になる理由として、策定者の力量不足が挙げられます。PMOや有識者とのレビューを行い、タスクの抽出漏れをなくしても、プロジェクトマネージャーが見積精度を見誤る場合が該当します。例えば、リスクをおそれるあまり工数を過大に見積もったり、逆に不足したりするケースです。
特に、ノウハウがない新技術を利用する場合も見誤りやすいポイントの1つです。対策としてはPMOや有識者による見積もりレビューが有効です。これはレビューの内容を見積もりに絞り妥当性を確認します。
遅延原因4:担当アサインのミス
プロジェクト遅延の原因として、担当アサインのミスが挙げられます。プロジェクトメンバーを選出するにあたって、必要なスキルを持った要員が集まらなかったり、別のプロジェクトに取られたりする場合があります。求めたスキルを持つ要員が集まらない場合は、既に当初のスケジュールより遅れている状態です。
対策としては、スキルを補完するようにテックリードへ技術面のサポートを依頼したり、成果物のレビューを充実させたりする対策が有効です。育成を兼ねたプロジェクトの場合、教育係を任命し、ペアで取り組む方法もあります。
理由:人員不足
担当アサインのミスとなる理由として、人員不足が挙げられます。プロジェクトチームを編成する際に、必要なスキルを持った人員が集まらないケースです。この場合、当初のスケジュール通りプロジェクトが進行することはほぼありません。人員不足の対策としては以下の3つがあります。
対策 | 注意点 |
|---|---|
現在集められる人員で進めた想定でスケジュール を引き直す | スキルが不足しているメンバーで行うため進捗管理を しっかり行う必要がある |
外部より必要なスキルを持った人材を派遣してもらう | スキルのある要員が見つからない可能性がある。 |
必要なスキルを利用した部分を外注する | 外注先の管理と進捗の確認は必ず必要。外注禁止の契約の 場合もあるため、この方法が必ず使えるとは限らない |
これらの対策を行った場合、当初のスケジュールよりもコストが高くなる場合がほとんどです。プロジェクトの成功判定として利用するQCDのC(COST:コスト)に悪影響を与えるため、ステークホルダーへ相談し、承認してもらう必要があります。また、外注する場合は契約違反にならないように、外注禁止の条文がないか契約書を必ず確認しましょう。
遅延原因5:遅延発生時の対応ミス
プロジェクト遅延の原因として、遅延発生時の対応ミスが挙げられます。どのプロジェクトも、何らかの遅れが発生し、計画通りに進むことはほとんどありません。遅れが発生した時に最も重要な点は、いかに迅速に対応できるかです。
問題点をいち早く分析し、対策を立て、実行に移せるかでプロジェクトの成功確率が変わってきます。遅延が発生したときに最もやってはいけないことは、「放置」と「自分たちだけで何とかしよう」とすることです。
対策としては、速やかにステークホルダーに報告する点と、自分たちだけで対応するのではなく、ステークホルダーやプロジェクト全体で対応するという意識を広める点になります。
遅延原因6:不測の事態の発生
プロジェクト遅延の原因として、不測の事態の発生が挙げられます。どれだけリスク対策を行っていても、自然災害やパンデミックといった不測の事態が発生する場合があり、回避が困難です。企業としてBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)や、緊急時の対応マニュアルを備えていても対応できない場合もあります。
この場合の対策は多くありません。やむを得ないものと考え、発生した場合はステークホルダーへ報告し、顧客を含めて対応を協議した方が良いでしょう。
理由:メンバーの病欠
不測の事態の発生となる理由として、メンバーの病欠が挙げられます。この場合は、代替要員の確保により対応可能です。ただし、新しいメンバーは今までプロジェクトで共有できていた情報を持っていないため、新メンバーがプロジェクトの軌道に乗るまでは、情報共有を密にする必要があります。
また、チームに溶け込めるようチーム内コミュニケーションを頻繁に行い、協力的な雰囲気の醸成が必要です。例えば、定期的なミーティングやチャットツールを活用した日常的なコミュニケーションを行うことで、新メンバーがチームに馴染みやすくなります。
遅延原因7:要件定義が曖昧
プロジェクト遅延の原因として、要件定義が曖昧なことが挙げられます。要件定義が曖昧で成果物が明確に定まらないケースです。成果物が明確になっていないため、これらがプロジェクトの途中で変更され、スケジュールに大きな影響を与えるおそれがあります。
対策としては、顧客との要件定義をしっかり行い、要件定義書といった形にして、顧客からの承認をもらい共通認識を持つことが有効です。
遅延原因8:リカバリのミス
プロジェクト遅延の原因として、リカバリのミスが挙げられます。プロジェクトの遅延に対するリカバリを誤り、更に事態を悪化させるケースが該当します。プロジェクト遅延の状態では、早くプロジェクトを正常に戻したい意識が強く働き、焦りが生じて更なるミスを誘発しがちです。
対策としては、まず一旦落ち着くことです。一旦落ち着いてリカバリ方法を策定し、有識者と協議の上でリカバリする方法が有効になります。
理由:リカバリ策は万能ではない
リカバリのミスの理由として、リカバリ策は万能ではないことが挙げられます。例えば、納期直前に重大な品質の瑕疵が発見された場合、成果物は修正すればよいですが納期に間に合わないケースがあります。このような状況では、リカバリ策が十分に機能しません。
リカバリ策が効果を発揮するためには、適切なタイミングとリソースが必要です。そもそも、リカバリできないケースもあり、リカバリ策は万能ではありません。
このようなケースは、代替策の検討や納期の変更交渉、顧客の要求に間に合うような段階的なリリース等、柔軟に対応していく必要があります。PMOやステークホルダーとの会議を開催し、今後の対応について検討しましょう。
プロジェクト遅延をリカバリする方法
プロジェクトは大小の遅延が発生するものです。遅延が発生した時に、正常なスケジュールに戻すためにリカバリを行います。リカバリに失敗すると、より困難な状況になる場合が多いため、リカバリ方法は慎重な選定が必要です。ここではリカバリの方法を紹介します。
プロジェクトのリカバリとは
プロジェクトのリカバリとは、遅延状態にあるプロジェクトを正常な状態に戻すことを指します。どれだけプロジェクト開始時のタスク分割やリスク管理を正確に行っても、何らかのプロジェクトの遅延は発生します。最も重要なのは、プロジェクト遅延に対し問題を冷静に分析し対応する点です。
クラッシング
プロジェクト遅延をリカバリする方法としてクラッシングがあります。クラッシングとは、リソースの追加投入により工期を短縮する手法です。たとえば、1人で5日分のタスクの場合、単純に考えると2人投入すれば2.5人日の工期短縮が可能です。これによりプロジェクトの遅延を短縮し正常な状態に持っていきます。
クラッシングは、クリティカルパスと呼ばれる、他のタスクと依存関係がありプロジェクト全体のスケジュールに影響を与える可能性の高い工程で行わなければ、十分な効果が得られません。
注意点として、単純に資源を増員したからといって工期を必ず短縮できない点です。要員のスキルや経歴はもちろん、プロジェクトの規約、累積された共有情報を正確に理解してもらう必要があります。投入された人員がスキル不足の場合、教育やチェックに時間を取られ、かえって遅延を拡大させる要因になりかねません。
この場合は、既存のチームメンバーが残業したり、ツールを導入したりして時間短縮を行う方が有効な場合もあります。これもクラッシングの1つです。
クラッシングは経費の増大を含むため、コスト管理も重要になります。クラッシングは有効な方法ですが、対費用効果を考慮して最良な方法を選択しましょう。
ファスト・トラッキング
ファスト・トラッキングとは、タスクを後続のタスクと同時並行して進める方法です。タスクの完了を待つことなく次のタスクを進めるため、待ち時間の必要がなく大幅な工期短縮が可能です。ただし、後続のタスクは現在進行中のタスクの成果物をもとに作成しているため、前のタスクの成果物に変更が発生した場合、後続の成果物にも変更を行わなければならなくなります。
場合によっては、ファスト・トラッキングで進めた後工程の作業が、すべて無駄になるケースもあるでしょう。また、ファスト・トラッキングは前後の工程で同時に成果物を作成するため、品質の管理が非常に難しくなります。
ファスト・トラッキングの利点としては、工期を短縮できる点と、プロジェクトの進行を早められる点です。しかし、リスクもあるため慎重に検討して採用するか否かを決定しましょう。
要件の見直し
要件が曖昧な場合、目標や成果物が明確に定まらず、作成途中で変更が生じたり、顧客が望むものにならなかったりするおそれがあります。場合によっては納品した成果物が顧客要求と異なり、作成し直す事態になるケースもあり得ます。目標や成果物に齟齬が出ないように、まずは要件を明確にする点が重要です。
プロジェクトの遅延防止策
プロジェクトを推進するにあたり、プロジェクトの遅延はなるべく避けたいものです。プロジェクトを遅延させないための防止策を取り入れることで、遅延の発生を抑えたり、遅延する期間を短くしたりできます。ここではプロジェクトの遅延に対する防止策を紹介します。
情報共有をこまめにする
情報共有をこまめにすることは、プロジェクトの遅延防止策として有効です。プロジェクトは進んでいくにつれて、想像もしていない問題やリスクが発生します。その問題やリスクをいち早く察知し、対策を講じることは極めて有効な遅延防止策です。
そのためには、情報共有をこまめに行い、チームメンバーと連携することが重要です。チームメンバーの誰かが気付いた問題やリスクをプロジェクトマネージャーやプロジェクトリーダーに報告し、問題やリスクを認知して、初めてプロジェクト遅延の対応が可能となります。
チームメンバーは指示を受けて作業するのではなく、一丸となってプロジェクトを推進するという雰囲気の醸成が重要です。また、PMOの定期的な開催も有効な防止策です。PMOにて進捗報告した際に、微細な遅れや今まで経験した遅延から、有効な遅延防止方法や対処方法の支援が期待できます。
プロジェクト管理ツールの導入
プロジェクト管理ツールの導入も有効な遅延防止策です。プロジェクト管理ツールを利用することで、プロジェクトの進捗が可視化され、遅延や問題点が一目でわかるようになります。遅延している期間や、タスクの依存関係も明らかになるプロジェクト管理ツールもあります。
プロジェクト管理ツールの導入のメリットは非常に大きく、プロジェクト遅延の防止策以外にもタスク管理やリスク管理として有効です。プロジェクト管理ツールはたくさんの種類があるため、自社のプロジェクトに応じたプロジェクト管理ツールを選定し、プロジェクト遅延を防止しましょう。
プロジェクトの遅延原因まとめ
プロジェクト遅延とは、「プロジェクト」が納期に間に合わずに遅れることを言います。プロジェクト遅延により、顧客への損害や自社の信用失墜、機会の損失等、甚大な被害を受けるおそれがあります。
これらの遅延を防止するために、失敗の原因や理由をよく理解し、同じ状態にならないようにしましょう。また、遅延が発生したときに適切なリカバリ方法を取り入れ、ダメージが最小限になるようにコントロールしましょう。
コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング
コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。
クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由
②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供
③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス
クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事

PMO
プロジェクトリーダー(PL)の役割とは?PMとの違いと4つの仕事内容を解説
プロジェクトリーダー(PL)の役割とは何か、PMとの明確な違いと具体的な4つの仕事内容を解説。現場のチームを率いるPLに求められる必須スキルや、その重要性についてもわかりやすく説明します。

PMO
プロジェクトリーダー(PL)とは?PMとの違い・役割・必要なスキルを解説
プロジェクトリーダー(PL)とは何か、その役割やPMとの明確な違いを徹底解説。具体的な仕事内容から、PLに求められる3つの必須スキル、そしてSEからのキャリアパスまで、現場のリーダーを目指すすべての方に必要な情報を網羅します。

PMO
SEとPMの違いとは?仕事内容・スキル・年収を徹底比較【キャリアパスも解説】
SEとPMの違いを、仕事内容、必要なスキル、年収、責任範囲など5つの軸で徹底比較。SEからPMを目指すための具体的なキャリアパスや、求められるスキルの転換についても詳しく解説します。

PMO
認定スクラムマスター(CSM®)とは?取得方法・費用・難易度まで徹底解説
認定スクラムマスター(CSM®)とは何か、その価値と具体的な取得方法を徹底解説。必須となる研修内容から費用、試験の難易度、資格の更新方法まで網羅し、PSM™との違いも紹介します。

PMO
スクラムマスターの役割とは?仕事内容と3つの支援対象をスクラムガイドに基づき解説
スクラムマスターの役割と仕事内容を、公式ルールブックであるスクラムガイドに基づき徹底解説。開発者、プロダクトオーナー、組織という3つの支援対象への具体的な関わり方を紹介します。

PMO
スクラムマスターのおすすめ資格3選|CSMとPSMの違いを徹底比較【2025年最新】
スクラムマスターに関するおすすめの資格を徹底解説。世界的な二大資格であるCSM®とPSM™の違いを8つの軸で比較して紹介します。

PMO
プロダクトマネージャー(PdM)とは?仕事内容・役割からなり方まで解説
プロダクトマネージャー(PdM)とは何か、その仕事内容や役割、プロジェクトマネージャー(PM)との違いを初心者にもわかりやすく解説します。

PMO
テックリードとは?役割や仕事内容、エンジニアリングマネージャーとの違いを解説
テックリードとは何か、その役割や仕事内容、そしてエンジニアリングマネージャー(EM)との明確な違いを解説します。求められるスキルから、テックリードになるためのキャリアパスまで、現代の開発チームに不可欠なこの役割の全てがわかります。
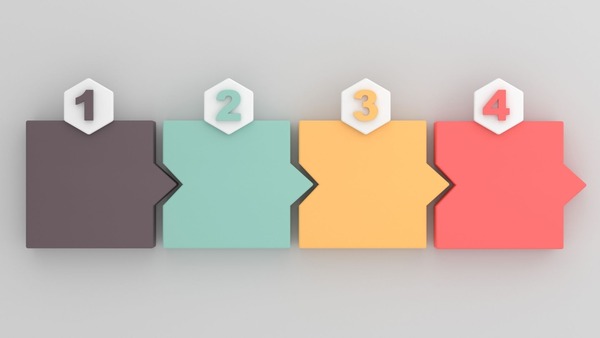
PMO
ロードマップとは?作り方の5ステップと種類別のテンプレート
ロードマップの正しい意味と作り方を解説。プロジェクト計画(ガントチャート)との明確な違いから、作成する目的、具体的な5つのステップ、種類別のテンプレートまで網羅的に紹介します。

PMO
ITプロジェクト管理とは?成功に導く5つのコツとおすすめツールを解説
ITプロジェクトがなぜ難しいのか、その理由から、成功に導く5つの具体的なコツ、そして開発手法の選び方やおすすめの管理ツールまで、専門家が分かりやすく解説します。































