Magazine
Quantsマガジン
ERPとは?意味や特徴とシステムの導入メリット・選び方を解説!
ERPとは、企業の資源を一元管理することで企業活動の効率化を図る考え方や、そうした考え方にもとづいて開発されたシステムのことです。本記事では、ERPの意味や特徴、システム導入のメリット・デメリット、製品を選ぶ際のポイントについて丁寧に解説します。
ERPの意味
ERP(Enterprise Resource Planning)は、直訳すると企業戦略計画であり、企業の資源を一元管理することで効率よく企業活動を行うという経営の考え方を意味します。
現在は、企業の資源を一元管理し有効活用することを目的に作られた統合基幹業務システムを、ERPと呼ぶことが多いです。
従来は、基幹業務ごとに各部門が基幹システムを構築し管理するという構成が主流でした。しかし、取り扱うデータ量やシステム数の増加などにより、データ連携やシステム同士の接続などの面で課題があがるようになりました。
そこで業務効率化のために生まれたのが、ERPです。
ERPの特徴
ERPは会計処理や人事手続き、生産・販売管理など、従来個別の基幹システムで管理していた業務を統合的に効率よく管理できる点が特徴です。
企業活動に関わる業務をERPで統合管理することによって、各業務における処理の連携やデータの分析、有効活用などが可能になり、業務効率化を図ることができます。
また、ERPの導入は、 手作業によるデータ連携作業の削減や、システム間での情報の不整合の防止などに役立ちます。その結果、企業のデジタル化を加速できる点も特徴です。
ERPの機能
ERP製品は複数の企業がリリースしており、製品によって機能は異なります。多くのERP製品が備えている主な機能は、以下のものがあげられます。
- 人事管理:採用や人事評価などの管理
- 労務・給与管理:従業員の勤怠や福利厚生の管理、給与の処理
- 顧客管理:顧客の個人情報や、取引履歴、問合せ履歴の管理
- 販売管理:見積、受注、出荷などにかかる処理や、売上情報の管理
- 生産管理:製品の製造や品質の管理
- 購買管理:企業で必要な資材の調達業務の管理
- 会計管理:財務会計や管理会計の管理
- 営業管理:顧客の情報や営業担当のタスク・スケジュール管理
これらの機能をすべて備えているERP製品もあれば、一部機能のみを備えているERP製品もあります。企業の規模や業務内容に応じて、必要な機能を備えたERP製品の選択が必要です。
ERPと基幹システムの違い
基幹システムは、各部門や部署が自組織の業務を管理するために導入する独立したシステムです。一方、ERPは企業活動に関わる業務を一元管理できる基幹業務の統合管理システムです。
ERPは、企業の重要な資産であるヒト、カネ、モノを一つのシステムに集約して管理します。そのため、独立した基幹システムを個別に管理するよりも、業務の効率化や部門間の連携、経営状況の可視化などを推進できるという違いがあります。
ERPの種類
ERPは、開発手法や導入形態、ERPシステムのサーバーの運用方法によって、様々な種類が展開されています。
ERPの開発手法による種類分け
ERPの種類は、ERPシステムがどのような手法で開発されたかによって、次の3つに分類することができます。
オープンソース型
オープンソースとは、ソースコードが一般に公開されており、無償で利用できるソフトウェアやシステムです。
オープンソース型のERPは、システムの構築に必要なソースコードが無償で公開されており、導入時は利用者側でシステムの構築作業等を実施する種類を指します。
無償でソフトウェアを入手できる分、導入時のコストを削減することができる点がオープンソース型のERPのメリットです。
また、システムの構築を自社で実施する必要があるため、拡張性が高く、自社用にカスタマイズしやすい点も特徴です。一方で、構築やカスタマイズのためには、スキルをもったエンジニアやシステム運用者が必要になる点に注意が必要です。
自社や業務委託先にオープンソース型ソフトウェアの運用に関するナレッジやスキルをもった人材がおり、安価にERPを導入したい企業は、オープンソース型のERPを検討するとよいでしょう。
スクラッチ型
システム開発の世界においてスクラッチ開発とは、ソフトウェアやシステムをゼロから作り出す手法です。
スクラッチ型のERPは、企業の要件に合わせてゼロから構築するスクラッチ開発の手法を用いて開発される種類を指します。
オーダーメイドで構築するため、企業特有の業務や特殊な要件にも対応できる点がメリットです。また、一度構築・展開が完了すれば、基本的に年間のライセンス料などはかからず運用できます。
そのためパッケージ型ERPと比較して、開発後に改修や機能拡張を実施したとしても、ランニングコストを安価に抑えられる傾向にあります。
一方でシステムをゼロから構築するため、イニシャルコストが高額になり、展開までに時間がかかるという特徴があります。
パッケージ型のERPではカバーできない要件が多い企業は、スクラッチ型のERPを検討するとよいでしょう。
パッケージ型
パッケージ型のERPは、一般的に企業活動において必要な業務をベースにした標準的な機能がパッケージ化されて提供される種類を指します。
初期導入時の開発工数が抑えられるため、スクラッチ型のERPと比べて安価なイニシャルコストで導入できる点がメリットです。
開発ベンダによって、導入や運用方法が手順化されており、導入後のサポート体制も整っていることから、導入者や利用者側の負荷を軽減できる点も特徴です。
一方で、年間のライセンス料がかかる点や、パッケージをカスタマイズする場合の追加コストがかさむ可能性がある点には注意が必要です。
独自の要件が少なく、標準的なERP製品を短期間で導入したい企業は、パッケージ型のERPを検討するとよいでしょう。
ERPの導入形態による種類分け
ERPの種類は、システムの導入形態によって次の4つに分類できます。
業務ソフト型
業務ソフト型のERPは、特定の業務に絞って導入される種類です。会計システムや人事・労務システムなど、一部の領域に特化して業務を一元管理することを目的とします。
導入範囲が絞られる分、導入コストやランニングコストは安価にすむ点がメリットです。
一方で、一部業務の統合管理にとどまるため、企業全体での業務効率化や経営可視化の観点では大きな導入効果を得られない可能性があります。
クラウド型
クラウド型のERPは、自社内ではなく、クラウド事業者の環境上に構築される種類です。ERPの利用時は、自社からクラウド環境にアクセスし、システムを利用することになります。
基本的に自社内での開発は不要であり、運用もクラウド事業者のサポートを受けられるため、利用者側の負荷が少なく導入しやすい点が特徴です。
コンポーネント型
コンポーネント型は、自社で必要な機能(コンポーネント)のみに対象を絞って導入する種類です。
ERPの機能は、会計、人事、生産、営業管理など多岐に渡りますが、そのうち必要なもののみを組み合わせて導入します。既存の基幹システムがある領域は導入を見送ったり、企業の規模に合わせて機能を絞ったりすることができます。
幅広い機能を備える統合型と比べて、予算や要件にあった範囲で導入できる点がメリットです。
一方で、選択したコンポーネントのみ一元管理となるため、ERP導入のメリットである業務効率化などの効果が限定される点には注意しましょう。
統合型
統合型のERPは、企業活動に関わる幅広い業務の機能を備えた種類です。
会計、人事、生産、営業管理など、複数の業務をひとつのシステムで統合的に管理するため、業務間のデータの連携ミスの削減や、経営状況の可視化、データの有効活用等のメリットを享受しやすい点が特徴です。
一方で、部門横断的に基幹システムを統合する必要があるため、導入時の要件定義や部門間の調整等に時間を要し、導入コストがかさむ可能性があります。
ERPサーバーの運用方法による種類分け
ERPの種類は、ERPのサーバーの運用方法によって、次の3パターンに分けられます。
オンプレミス型
オンプレミス型のERPは、自社内にシステムを構築し、運用する種類を指します。
自社内にシステムを構築するため、自社環境にある既存のシステムやソフトウェアとの連携がしやすい点が特徴です。また、システムの改修や拡張機能の追加開発などを行いやすいという点がメリットです。
一方で、自社の環境に合わせた設計・構築が発生する分、導入コストがかさむ傾向にあります。
クラウド型
クラウド型のERPは、自社内ではなくクラウド事業者の環境上に構築される種類です。
基本的に自社内での開発は不要であり、運用もクラウド事業者のサポートを受けられるため、利用者側の負荷が少なく導入しやすい点が特徴です。障害対応やシステムメンテナンスなども、クラウドサービス事業者に任せることが可能です。
一方で、クラウド事業者の環境上にシステムが構築されるため、自社環境内のシステムと連携できない可能性がある点や追加開発に関して制約がある点には注意しましょう。
ハイブリッド型
ハイブリッド型は、クラウド型とオンプレミス型を組み合わせた種類です。
ハイブリット型を採用する場合、拠点や機能によってオンプレミス型かクラウド型かを使い分ける運用が可能です。
オンプレミス型かハイブリット型かを使い分ける基準がないまま導入すると、構成が複雑になり運用コストがかさむ可能性があるため注意しましょう。
ERPの導入メリット
ERPの導入は、企業に様々なメリットをもたらします。こちらでは、代表的なメリットを8つ説明します。
メリット1:イノベーションの創出
ERPの導入によって業務効率化が進むと、事務的な作業時間が削減され、従業員はより創造力が求められる業務に集中できるようになります。
また、企業活動に関わる情報が統合されることで部門間のコラボレーションが増え、コミュニケーションが活発になりやすいです。
その結果、DX(デジタルトランスフォーメーション)が進み、イノベーションの創出につなげることができるでしょう。
メリット2:業務の効率化
ERP導入の主なメリットは、業務の効率化です。各基幹システムが個別に管理されている場合、複数の基幹システムに重複するデータを入力する手間がかかったり、基幹システム間でデータの不整合が発生したりすることがあります。
ERPを導入し、一つのデータベースでデータを一元管理することで、こうした無駄な作業や入力ミス等を減らし、業務効率化を図ることができます。
メリット3:経営状況の可視化
企業の経営層が経営状況を把握することを目的にまとめられる会計を管理会計と呼びます。ERPの導入は、この管理会計業務に有用です。
ERPによって業務横断的なデータを一元管理することで、予算や売上、業績情報などの経営判断に必要な情報を統合的に可視化できます。
メリット4:システム運用負担の軽減
部門ごとに独自に基幹システムを開発する場合、各システムごとにパッチの適用やバージョンアップ対応といった運用作業が必要です。
一方でERPを導入すると、こうした運用作業を統合し、運用者の負荷を軽減することができます。
また、クラウド型のERPの場合、こうした運用作業をクラウドサービス事業者に任せられるというメリットがあるため、より運用負担を低減できます。
メリット5:情報の一元管理
ERPを導入すると、データベースが一つに統合され、情報を一元管理することが可能になります。これによって、従来分断されていた各業務データが統合され、ビックデータ分析などによるデータの分析・活用が促進されるという点は、ERP導入の大きなメリットです。
メリット6:成功企業のノウハウ活用
パッケージ型のERPを提供するベンダは、過去の実績にもとづいて企業の業務効率化や内部統制の強化に有用な機能をパッケージとして展開しています。
他社で活用されているテンプレートやパッケージ、ERP製品ベンダに蓄積されたノウハウを活用して企業の業務改革に取り組める点は、ERP導入のメリットです。
メリット7:内部統制の強化
内部統制とは、企業を健全に運用するための仕組みです。
ERPでデータを一元管理することで、各基幹システム間で重複処理によるミスの削減や、アクセス権限管理の統合によるセキュリティの強化など、内部統制に有効な効果を期待できます。
また横断的に業務や経営状況を可視化し、承認フローや監視体制を統合することで、不正行為の防止も期待できます。
メリット8:他のシステムとの連携
ERPが普及する前は、基幹システムが独立して運用されていました。そのため、システム間で重複するデータの入力が必要な場合やデータの連携が必要な場合に、その都度手間がかかっていました。
しかし、ERPを利用することで業務システムが自動的に連携され、効率的にデータの分析や部門間のコミュニケーションを行うことができるようになります。
ERPのデメリット
ERPの導入には多数のメリットがある一方で、導入時に留意すべきデメリットもあります。
デメリット1:業務フローの見直し
ERPを導入するためには、既存の基幹システムや業務を整理して、ERPを組み込んだ業務フローへ修正する必要があります。
ERPに統合する業務領域が幅広く、取り扱うデータの種類が多岐に渡るほど、大規模な既存業務の見直しが発生します。
デメリット2:システムの選び方が難しい
ERP製品は、開発手法(スクラッチ型、パッケージ型等)や導入形態(コンポーネント型、統合型等)、搭載機能に応じて、様々な種類が展開されています。
そのため、導入の目的や期待する効果、要件を明確にしないと製品選びが難しいです。ERPの知見をもつ専門家と要件を確認し、予算に見合った製品を選ぶようにしましょう。
デメリット3:導入コストが高め
ERPの導入時は、製品の購入費用や開発費用などがかかり、特にカスタマイズの要件がある場合は導入コストが高額になる傾向になります。
また、社内にERP製品に精通している人材がいない場合、人的リソースの確保に関する費用も追加で必要です。
デメリット4:導入のための説得
ERPの導入によって複数の業務・データを一元管理する場合、各部署との調整が必要です。ERP製品の要件のヒアリングや現行業務フローの見直し、ERP利用トレーニングの実施など、導入にあたって様々な対応を各部署に依頼する必要があり、導入に向けた説得に時間を要する可能性があります。
各調整先に前向きに対応してもらうためには、ERP導入の目的やメリット、期待される効果などを事前にきちんと整理しておくとよいでしょう。
ERPの選び方のポイント
ERP製品の種類は多岐に渡り、選ぶ際に見るべきポイントがいくつかあります。こちらで説明するポイントを参考に、自社にあった製品を選定しましょう。
インフラ形式
ERPのサーバーの運用方法には、オンプレミス型、クラウド型、ハイブリッド型があります。
オンプレミス型は、オンプレミス環境にある既存システムとの連携のしやすさや、システムの改修、追加開発のしやすさの点で優れています。一方で、開発コストが高額になりやすい点には注意が必要です。
クラウド型は、開発コストが安価な傾向にある点がメリットです。しかし、IaaSやPaaS部分のカスタマイズが難しく、オンプレ型と比べて柔軟さに欠けます。
こうしたインフラ形式ごとの特徴を踏まえた製品の選定が必要です。
カスタマイズ性
自社特有の組織形態や業務プロセス、ビジネスモデルがあり、パッケージ型のERPをそのまま適用できない場合は、カスタマイズします。
自社特有の要件が多い場合は、スクラッチ型で開発されるERPやオンプレミス型のERPを選ぶとよいでしょう。クラウド型のERPはカスタマイズの自由度が低いため、自社の要件を組み込めるかよく確認してください。
また、業界特有の商習慣などがある場合は、特定の業界に特化したERP製品の利用も検討するとよいでしょう。
サポート体制
ERPを開発・運用する場合、専門知識が求められます。ERPの導入後も、ユーザーからの問合せ対応や障害対応、追加開発の対応などが発生します。
特に、パッケージ製品のカスタマイズや追加開発をする場合は、製品仕様をよく理解しているエンジニアなどが必要です。
自社内にERP製品に精通している従業員がいない場合は、サポート体制が充実している製品を選ぶとよいでしょう。
オープンソース型のERPは、カスタマイズがしやすく柔軟性がある分、開発・運用者側が高いスキルを持っている必要があります。一方でパッケージ型のERPは、多くのベンダーが開発・運用のサポートも併せて提供しています。
自社でできること・できないことを整理し、ERP製品側のサービスや開発ベンダーにどういったサポートを依頼するべきか検討しましょう。
セキュリティ性
ERPは、企業活動に関わる様々なデータを集約して一元管理できるシステムです。経営に関する機密情報や顧客の個人情報など、重要なデータが大量に蓄積されます。その分、不正アクセスや内部不正などによってデータが外部に流出した場合のリスクが大きいです。
こうしたデータを守るために、セキュリティ性の高い製品を選ぶことをおすすめします。
ERPに統合する業務領域が幅広いほど、様々な部門の従業員がシステムにアクセスします。そのため、アクセス権の設定やデータの共有設定などが細かくできるか確認するとよいでしょう。
また、暗号化機能や認証機能についても、セキュリティ性の高い機能が実装されているか留意しましょう。
他社への導入実績
ERP製品は、国内の大手ベンダから中小ベンダ、また海外のベンダが提供しているものまで豊富な種類があります。
製品によっては特定の業界における導入実績に優れているものもあります。そのため、同業他社や同じ導入目的をもつ企業への導入実績があるか確認し、自社の業務やビジネスモデルにフィットする特徴をもった製品か確認しましょう。
開発を外部ベンダに委託する場合は、委託先のベンダの実績にも留意しましょう。
必要な機能の確認
ERPは、会計管理、人事管理、顧客管理、生産管理など、幅広い業務領域にわたって製品が展開されています。自社でERPを導入したい業務範囲と比較して、必要な機能が含まれているか確認しましょう。
予算との兼ね合い
標準機能が豊富な上位製品は、ライセンス費が高額です。また、スクラッチ型やオンプレミス型で複数のカスタマイズをする場合は、開発費用が高額になります。
大手ERPベンダが提供するERPは、初期導入費用に加えて、数百~数千万円の追加開発費用がかかることもあります。
一方で、クラウド型のERPはオンプレミス型と比べると安価な傾向にあります。
コストと期待される効果を整理して、費用対効果が高い製品を選びましょう。
ERP導入の流れ
ERPの導入は、既存業務の見直しに伴い現行環境への影響が大きいため、きちんと計画を立てて導入しないと現場の混乱を招きます。こちらでは、ERP導入の流れを説明します。
ERPの構想
まずは、ERP導入の目的や期待する効果を明確にします。どの業務を効率化したいか、どういった情報をERPで管理したいかなどを決めるとよいでしょう。
最初にERP導入の構想を明確にしておかないと、必要以上に機能を盛り込み開発費がかさんでしまったり、思うような導入効果を得られなかったりしてしまいます。
ERPの運用開始後に導入効果の測定をしやすいように、目標値を数値で定義しておくことをおすすめします。
ベンダーの選定
続いて、ERPの開発を担当するベンダーを選定しましょう。自社内にERPの有識者がいる場合は自社で開発できますが、大規模な業務改革を行う場合は専門家であるベンダーに委託する方がよいでしょう。
また、このとき自社内でERP導入の案件を担当するチームの体制も整えましょう。複数の業務をERPに統合する場合は各部署との調整などが必要になるため、他部署とのコミュニケーションをとって交渉できる人材をチームにいれることをおすすめします。
要件定義
ERPの導入において、要件定義は重要なステップです。現行の業務一覧を可視化し、どの業務をERPに移管するかスコープを定めます。そして、ERPに移管する場合の新たな業務フローを整理します。
ERPに移管する業務範囲や新たな業務フローを整理したら、ERPに必要な機能要件や非機能要件を定義します。
企業特有の組織体制や業務プロセスがある場合は、ERP製品のカスタマイズが必要になるかもしれません。洗い出した要件をカバーできる製品があるか調査し、ない場合はカスタマイズを検討しましょう。
また、ERPの想定利用ユーザーとも要件定義の内容を共有し、現場が必要としている機能が盛り込まれているか確認しましょう。
ベンダーによるERP開発
要件定義が完了したら、定義した要件にしたがってベンダーでシステムを構築します。既存システムとの連携など現行環境に影響がある作業をする場合は、事前に関連部署とスケジュールを調整して開発作業を進めます。
ERP導入テスト
開発が完了したら、システムのテストを行います。問題なくシステムが動作するかの確認はもちろん、実際の業務に不便が生じないか、ERPを組み込んだ業務フローに不具合はないか、という観点でテストをします。
また、既存の基幹システムからERPへ移行する場合は、データ移管に苦労するケースがあります。スムーズにデータ移行を実施できるか、入念にテストを行うとよいでしょう。
ERP運用準備
ERP導入テストが完了したら、運用体制を整えます。自社でシステムを運用する場合は運用チームを作り、開発ベンダーから引継ぎを受けます。システムの運用手順や障害対応方法の確認、ユーザーからの問合せ窓口の準備などが必要です。
また運用準備の中で、ERP利用ユーザー向けのトレーニング資材を用意するとよいでしょう。
ERP導入準備
ERPの試験導入に向けて、ERPや既存環境の設定変更を行います。また、ERP利用者への周知や説明会の実施、利用方法に関するトレーニングなどを行います。
ERP並行導入判定
ERPを試験的に導入し、ERPを組み込んだ新しい業務フローに問題がないか利用者目線で確認します。利用者にヒアリングし、使いづらい点はないか、利用マニュアルやトレーニングの用意は十分かなどを見極めます。
はじめから全社的に試験導入すると、不具合があった際の業務影響が大きいです。まずは、展開範囲を一部の部門に絞ってパイロット運用を行うとよいでしょう。
ERP本格導入
ERP並行導入判定にて本格導入可能と判定したら、全社的に本番展開します。既存の基幹システムからERPに切り替える場合は、万が一不具合が発生しても業務影響を最小限に抑えられる時間帯を選ぶなどして、慎重に本格導入を進めましょう。
運用・保守
ERPの本番展開後は、運用・保守を行います。
ERPは企業の機密データを取り扱うため、定期的なパッチ適用やシステムのバージョンアップ対応を行い、セキュリティ性の高い状態を保つ必要があります。
また、ERPの構想フェーズで定めた導入目的や期待する導入効果を達成できたか、運用開始から一定期間たった時点で測定するとよいでしょう。
目標を達成していない場合や効果が思うようにあがっていない場合は、課題を調査し機能改善や追加開発を検討する必要があります。
ERPまとめ
ERPとは、企業の資源を一元管理することで企業活動の効率化を図る考え方や、そうした考え方にもとづいて開発されたシステムのことです。
ERPの機能は多岐に渡り、人事管理や会計管理、生産管理など企業活動に関わる様々な業務を効率よく統合管理できる点が特徴です。
ERP導入によって、業務効率化や経営状況の可視化、内部統制の強化といったメリットを享受できます。一方で、現行の業務フローの見直しが必要であり、ERPに統合する業務領域が幅広いほど導入コストが高額になる点には注意が必要です。
近年国内ベンダのものだけでも数十程度のERP製品があるため、製品選定時は予算に見合う範囲で標準機能やインフラ形式、カスタマイズ性といった製品の特徴を比較し、費用対効果が高いと見込まれる製品を選定しましょう。
コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング
コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。
クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由
②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供
③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス
クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事

PMO
プロジェクトリーダー(PL)の役割とは?PMとの違いと4つの仕事内容を解説
プロジェクトリーダー(PL)の役割とは何か、PMとの明確な違いと具体的な4つの仕事内容を解説。現場のチームを率いるPLに求められる必須スキルや、その重要性についてもわかりやすく説明します。

PMO
プロジェクトリーダー(PL)とは?PMとの違い・役割・必要なスキルを解説
プロジェクトリーダー(PL)とは何か、その役割やPMとの明確な違いを徹底解説。具体的な仕事内容から、PLに求められる3つの必須スキル、そしてSEからのキャリアパスまで、現場のリーダーを目指すすべての方に必要な情報を網羅します。

PMO
SEとPMの違いとは?仕事内容・スキル・年収を徹底比較【キャリアパスも解説】
SEとPMの違いを、仕事内容、必要なスキル、年収、責任範囲など5つの軸で徹底比較。SEからPMを目指すための具体的なキャリアパスや、求められるスキルの転換についても詳しく解説します。

PMO
認定スクラムマスター(CSM®)とは?取得方法・費用・難易度まで徹底解説
認定スクラムマスター(CSM®)とは何か、その価値と具体的な取得方法を徹底解説。必須となる研修内容から費用、試験の難易度、資格の更新方法まで網羅し、PSM™との違いも紹介します。

PMO
スクラムマスターの役割とは?仕事内容と3つの支援対象をスクラムガイドに基づき解説
スクラムマスターの役割と仕事内容を、公式ルールブックであるスクラムガイドに基づき徹底解説。開発者、プロダクトオーナー、組織という3つの支援対象への具体的な関わり方を紹介します。

PMO
スクラムマスターのおすすめ資格3選|CSMとPSMの違いを徹底比較【2025年最新】
スクラムマスターに関するおすすめの資格を徹底解説。世界的な二大資格であるCSM®とPSM™の違いを8つの軸で比較して紹介します。

PMO
プロダクトマネージャー(PdM)とは?仕事内容・役割からなり方まで解説
プロダクトマネージャー(PdM)とは何か、その仕事内容や役割、プロジェクトマネージャー(PM)との違いを初心者にもわかりやすく解説します。

PMO
テックリードとは?役割や仕事内容、エンジニアリングマネージャーとの違いを解説
テックリードとは何か、その役割や仕事内容、そしてエンジニアリングマネージャー(EM)との明確な違いを解説します。求められるスキルから、テックリードになるためのキャリアパスまで、現代の開発チームに不可欠なこの役割の全てがわかります。
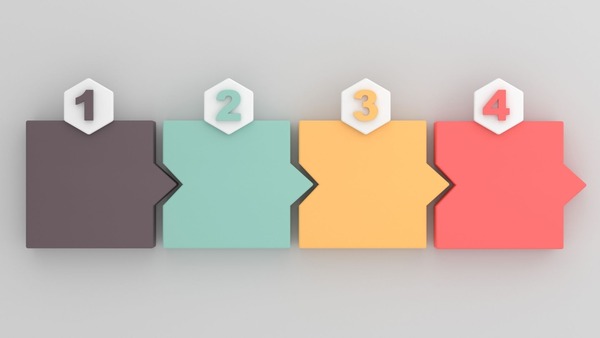
PMO
ロードマップとは?作り方の5ステップと種類別のテンプレート
ロードマップの正しい意味と作り方を解説。プロジェクト計画(ガントチャート)との明確な違いから、作成する目的、具体的な5つのステップ、種類別のテンプレートまで網羅的に紹介します。

PMO
ITプロジェクト管理とは?成功に導く5つのコツとおすすめツールを解説
ITプロジェクトがなぜ難しいのか、その理由から、成功に導く5つの具体的なコツ、そして開発手法の選び方やおすすめの管理ツールまで、専門家が分かりやすく解説します。































