Magazine
Quantsマガジン
脆弱性とは?意味や危険性と発生原因・対策を徹底解説!
脆弱性の意味は、システムにとって重大な危険性をもたらす設計上の欠陥や誤りです。近年、脆弱性が発見されるとすぐにサイバー攻撃に悪用されるケースも増えています。脆弱性を放置するリスクについて、事例をもとに原因を確認し、適切な対策を実施しましょう。
脆弱性(ぜいじゃくせい)とは?
脆弱性とは、システムやソフトウェアにおけるセキュリティ上の欠陥を指します。例えば、プログラム不具合や設計上のミスなどです。これは、本来意図されていない動作や情報漏洩などが起こる可能性があり、攻撃者による不正アクセスの原因になります。
脆弱性の一つにセキュリティホールがあります。脆弱性に対して、セキュリティホールは脆弱性を悪用して攻撃者が侵入できる具体的な穴です。つまりセキュリティホールは、脆弱性による具体的な欠陥と言えるでしょう。
また、脆弱性が発見された場合、開発元から脆弱性に関する情報やセキュリティパッチが公開されます。セキュリティパッチが公開されたら、速やかな適用の実施が必要です。
脆弱性を放置していた場合、日々巧妙化するサイバー攻撃のターゲットになる可能性が非常に高くなります。
脆弱性の意味
脆弱性は、セキュリティの分野において、コンピュータシステムやソフトウェアに存在する不完全な誤りなどを意味します。これらの脆弱性を悪用して、システムの侵入や情報の窃盗、サービスの妨害などをするのが攻撃者の手口です。
脆弱性などの設計上の欠陥や脆弱性を抱えている状態は、攻撃リスクを招く要因となります。具体的な被害の可能性を以下にまとめました。
- 不正アクセス
- マルウェア感染による情報窃取や改ざん、破壊
- アカウントの乗っ取り
- サービスやシステムの停止
開発元からの脆弱性の発見情報公開から、セキュリティパッチの配布まで時間を要します。セキュリティの観点から脆弱性が発見された場合、放置せずにリスクを認識して速やかに修正することが重要です。
セキュリティホールとの違いは?
セキュリティホールと脆弱性の違いは、プログラムの根本的な欠陥と、脆弱性を悪用して攻撃者が侵入できる具体的な穴です。
厳密に言うと、セキュリティホールは脆弱性の一種としてみなされます。セキュリティホールはシステムの欠陥などによって起こる不具合で、脆弱性とはシステムそのものに含まれる根本的な欠陥です。
脆弱性は構造的な欠陥であり、セキュリティホールを放置しておくと、不正アクセスやマルウェア感染などの被害につながります。さらに、システムダウンやコンプライアンス違反などの深刻な損害となり、日本でも脆弱性を悪用した事例が少なくありません。
脆弱性を放置する危険性
脆弱性を放置することは、重大なセキュリティリスクを引き起こす可能性があります。どのような危険性がもたらされるか、以下の4点にまとめました。
- 不正ログイン・不正アクセス
- データの盗聴や改ざん
- ウイルスの感染
- 他のシステムへ攻撃するための踏み台
また、開発元からの脆弱性情報の公開から、セキュリティパッチが配布されるまでに攻撃されることをゼロデイ攻撃といいます。脆弱性に対する攻撃スピードが上がっている近年、迅速な対応が必要です。
このように、脆弱性を放置することで多くのセキュリティリスクを引き起こすため、脆弱性の早期発見と対策をしましょう。
不正ログイン・不正アクセス
脆弱性を放置すると、脆弱性を悪用してシステムに侵入し、不正ログインや不正アクセスしやすくなります。例えば、脆弱性を悪用して認証システムに侵入し、アカウントを乗っとる攻撃手法です。
攻撃者はオペレーティングシステム(OS)やアプリケーション、ソフトウェアの脆弱性を突き、システムに侵入します。そこからさらに管理者権限のアカウント乗っ取りやマルウェアの仕込み、データの改ざんにターゲットを変える手口です。
こういった手口により、攻撃者が重要なデータやシステムへ不正なアクセスをし、被害を拡大させます。盗取された重要なデータには、顧客情報、個人情報、企業秘密情報などが含まれる可能性があり、被害は甚大です。
データの盗聴や改ざん
脆弱性を持つシステムでは、攻撃者によるデータの盗聴や改ざんのリスクが高まります。盗聴された情報が漏洩したり、改ざんされたデータに基づく誤判断につながるため注意が必要です。
例えば、攻撃者がウェブサイトに侵入し、悪意のあるプログラムを仕込むドライブバイダウンロードの攻撃などがあります。ユーザーがウェブサイトを閲覧する際に、自動的に悪意のあるプログラムがパソコンにダウンロードされる手口です。
これらは脆弱性を突いた攻撃であり、不正アクセスを糸口にして、データの盗聴や改ざんをしています。このように、システムやウェブサイトだけでなく、アプリケーションなどの脆弱性の放置も非常に危険です。
ウイルスの感染
脆弱性を持つシステムは、攻撃者のターゲットとなり、ウイルスやマルウェアに感染しやすくなります。ランサムウェアやトロイの木馬などは、マルウェアの一種であり、マルウェアは悪意のあるソフトウェアです。
これらのマルウェアは脆弱性を突いてコンピュータなどに侵入します。侵入後、重要データを盗んだり、システムをロックして身代金を要求したりする攻撃です。
さらに、システムを乗っ取ったり、重要なデータの窃取や破壊をしたり、他のシステムに攻撃を行ったりします。これにより、システムの機能停止や重要なデータの消失が引き起こされ、深刻な損害につながる危険性が高まるでしょう。
他のシステムへ攻撃するための踏み台
脆弱性を持つシステムは、他のシステムへの攻撃の踏み台として悪用されるケースがあります。攻撃者が脆弱性を悪用してシステム内に侵入し、情報やリソースから他のシステムへの侵入経路を探る手法です。
システムから他のシステムに攻撃を仕掛けることで、複数のシステムが攻撃の標的となり、さらに被害が拡大する危険性があります。
攻撃の中継地点として悪用されると、ウイルスの発生源となったり、攻撃者の追跡や特定が困難です。こういった不正アクセスを踏み台といいます。
脆弱性の発生原因
脆弱性は、ソフトウェアやシステムの開発過程で、プログラミングミスや設計上の欠陥など様々な要因によって発生します。主な脆弱性の発生原因は以下の通りです
- プログラミングミスやエラー処理の不備
- データ暗号化の不備や設計上の欠陥
- OSやソフトウェアの脆弱性
- 外部からのサイバー攻撃
- 人為的ミスや設定誤り
開発を行う際、プログラミングミスや設計上の欠陥が生じることがあります。具体的には、入力値のチェックやエラー処理の不足、要件定義の不備などの開発時の考慮不足が主な原因例です。
また、データ暗号化などのセキュリティ対策に関する考慮不足やOSの脆弱性、日々進化するサイバー攻撃によるものもあります。内外部からの攻撃に対するセキュリティ対策が不十分な場合、システムは脆弱性を抱えることになるため注意が必要です。
これらの原因を理解し、適切な対策や管理体制を講じることで、脆弱性の発生リスクを低減し、安全性を向上させることができます。
脆弱性を突かれた事例
セキュリティの強化や脆弱性の対策が不十分であることで、以下の脆弱性を突かれた事例があります。近年発生した代表的な脆弱性被害事例について、詳細な分析と考察を行います。
- PayPayの設定不備により加盟店情報が不正閲覧された可能性
- カプコンへの不正アクセス攻撃による情報の流出
- 愛媛大学への不正ログインによる大量の迷惑メールの送信
- LINEへの不正アクセスによる個人情報の流出の可能性
これらの被害は、コンプライアンス違反などの企業イメージ低下、大量の個人情報の漏洩や流出を招きました。
PayPayの設定不備により加盟店情報が不正閲覧された可能性
2020年に、PayPayが加盟店向けの管理画面において、不正ログインが検出された事例が報告されました。この事件では、不正アクセスした攻撃者が2000万件のPayPayの加盟店情報を閲覧した可能性があります。
この問題は、バージョンアップ作業による、アクセス権限の設定不備が原因です。閲覧権限のないユーザーの設定が不完全だったため、不正閲覧が可能になっていました。
PayPayの事例では、店舗名、住所、電話番号、売上情報などが不正閲覧された可能性があります。これは、アクセス制御設定という基本的なセキュリティ対策の不備が原因で発生しました。この事件は国内最大級の個人情報漏洩事件です。
カプコンへの不正アクセス攻撃による情報の流出
2020年、大手ゲームメーカーであるカプコンがサイバー攻撃を受け、顧客情報が流出したと発表しました。この攻撃では、外部からの不正アクセス者が内部システムに侵入し、顧客データや従業員の個人情報などが流出したとされています。
また国内外の拠点の一部機器が、乗っ取りやランサムウェア感染により暗号化されました。この問題は、カプコンのVPN装置の脆弱性を悪用した不正アクセス攻撃が原因です。攻撃者は、脆弱性を突いて社内システムに侵入し、情報を窃取したと考えられています。
カプコンは、問題発覚後すぐに原因調査を行い、脆弱性を修正した上で、再発防止策として、セキュリティ体制の強化や従業員への教育などを実施しています。
愛媛大学への不正ログインによる大量の迷惑メールの送信
2020年、愛媛大学のシステムが外部からの不正ログインを受け、大量の迷惑メールが送信されました。不正ログインした攻撃者が愛媛大学のメールサーバーに侵入し、学生や教職員のアカウントを乗っ取ったとされています。
この問題は大学が管理するメールサーバーのアカウント情報が漏洩し、不正ログインされたことが原因です。漏洩したアカウント情報を使用して、攻撃者はECサイトに誘導する約3万5000件の迷惑メールを送りつけました。
愛媛大学は再発防止策として、メールサービス利用時のセキュリティ強化やアカウント管理の徹底など、適切な対策を講じるとのことです。
LINEへの不正アクセスによる個人情報の流出の可能性
2023年、LINEヤフーは、約44万件の利用者情報が不正アクセスで流出した可能性があると発表しました。この不正アクセスは、韓国のIT企業「ネイバー」のシステムを踏み台に行われた可能性があります。
ネイバーの業務委託先がサイバー攻撃を受けたことで、共通化されているLINEのシステムも影響を受けたとのことです。流出した可能性がある情報には下記が含まれています。
- 利用者の年代や性別
- スタンプの購入履歴
- 社内や取引先の従業員の氏名
- 所属、メールアドレス
メッセージの内容や銀行口座、クレジットカードの情報は含まれていないとされています。LINEヤフーは、再発防止としてネイバーとシステムを分離し、管理を強化する方針を示しました。
脆弱性の確認・対策方法
脆弱性の確認や対策は、情報システムの安全を守るために重要な取り組みです。また、下記の観点で対策や確認を組み合わせ、効果的な脆弱性対策を実現できます。
- 脆弱性情報の収集
- 脆弱性診断(セキュリティ診断)の実施
- OSやソフトウェアを最新状態に更新する
脆弱性情報を収集し、個人や組織が脆弱性の対策をすることで、セキュリティを強化できます。これにより、セキュリティの脅威に対する防御力を強化し、潜在的なリスクを軽減可能です。
脆弱性情報の収集
これまでに様々な脆弱性が発見されており、信頼できる情報源を複数持って情報収集することで、セキュリティの強化が可能です。以下で、公開されている脆弱性情報を収集することができます。
- セキュリティベンダーや専門家から提供されるアップデート情報を定期的にチェック
- 脆弱性に関する情報が公開されているIPAのウェブサイトを参照
- セキュリティ情報ポータルなどで、最新の情報を確認
ITリテラシーの向上
ITリテラシーの向上は、個人や組織が脆弱性の持つリスクを軽減する上で不可欠です。社員教育を定期的に実施し、以下の方法でITリテラシーを向上させることができます。
- 従業員やユーザーに対して定期的なセキュリティ教育やトレーニングを行う
- セキュリティ意識を高めるための研修プログラムを実施する
- セキュリティに関する専門知識を持つ人材を雇用し、組織内でのセキュリティ意識を向上させる
脆弱性とは何か、被害や対策など、セキュリティに関する知識を身につけることが重要です。また、情報セキュリティに関する意識を高め、常に最新の脅威情報に注意を払いましょう。
脆弱性診断(セキュリティ診断)の実施
脆弱性診断は、システムやソフトウェアに潜む脆弱性を特定し、定期的に実施してセキュリティを維持する手法です。以下の方法で脆弱性診断を実施することができます。
- 内外部のネットワーク診断
- Webアプリケーション診断
- ペネトレーション(侵入)テスト
SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの脆弱性をスキャンする診断が有効です。また、ペネトレーションテストを行い、攻撃者の視点からシステムに侵入する手法を模倣して脆弱性を特定する方法もあります。
診断結果に基づいて、早期発見や被害の防止など適切な対策を講じることが重要です。脆弱性診断の結果を分析して、特定された脆弱性に対する対策や修正を実施しましょう。
OSやソフトウェアを最新状態に更新する
OSやソフトウェアを最新の状態に保つことは、脆弱性の基本的な対策です。以下の方法でOSやソフトウェアを最新状態に更新することができます。
- 自動更新の有効設定
- 定期的なメンテナンススケジュール設定
- アップデート通知を定期的に確認
OSなどの自動更新機能を有効にし、新しいセキュリティアップデートが自動的に適用されるようにします。また、セキュリティアップデートのリリース情報やセキュリティ通知を定期的に確認し、必要な対策を迅速に実施しましょう。
最新バージョンのソフトウェアを常に利用することで、脆弱性を修正することができます。さらに、自動更新機能を利用することで、最新バージョンに自動的に更新することが可能です。
脆弱性の対策をしよう!
脆弱性は、重大なリスクをもたらす深刻な脅威です。脆弱性を放置することは、情報漏洩やシステムダウンなどの被害につながる可能性があります。そのため、脆弱性を早期に発見し、適切な対策を講じることが重要です。
- 脆弱性情報の収集
- 脆弱性診断(セキュリティ診断)の実施
- OSやソフトウェアを最新状態に更新する
脆弱性診断とOSやソフトウェアの最新化は、セキュリティを強化し、潜在的な脆弱性を最小限に抑えるための重要な対策です。定期的に脆弱性診断を実施し、アップデートを行うことで、セキュリティレベルを維持し、セキュリティリスクを最小限にできます。
脆弱性対策は、継続的に行うことが重要です。定期的に脆弱性診断を実施し、最新の情報を収集し、必要に応じて対策を更新しましょう。
コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング
コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。
クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由
②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供
③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス
クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事

サイバーセキュリティ
マクロウイルスとは?オフィス製品に感染する仕組みと対策を解説!
マクロウイルスは、ビジネスに不可欠な「マイクロソフトオフィス」製品のマクロ機能を悪用するマルウェアの一種です。ここでは、マクロウイルスの特徴と感染経路や、具体的な種類と被害例、詳しい対策方法について解説します。感染の仕組みを理解して対策を講じましょう。

サイバーセキュリティ
サイバー攻撃とは?攻撃の目的・種類や手口と被害事例から対策を紹介!
サイバー攻撃とは、サーバやパソコンなどの機器に対して不正アクセスや情報窃取、破壊活動などを行う攻撃の総称です。近年はサイバー攻撃が高度化し、どんな組織もサイバー攻撃にあうリスクがあります。本記事では、サイバー攻撃の種類や手口、被害事例について詳しく解説します。
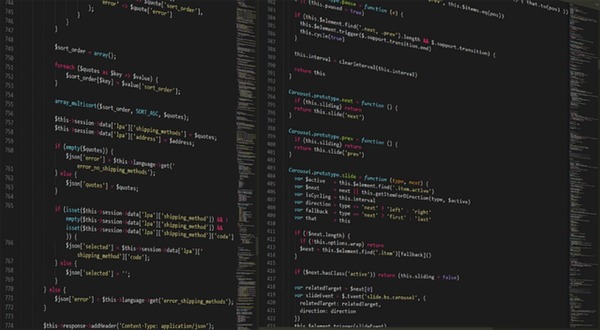
サイバーセキュリティ
VPNのセキュリティは安全?仕組みやメリットとリスクを解説!
本記事ではVPNのセキュリティについて解説しています。安全性と危険性、仕組み、メリット、さらにはリスクまで詳しく説明しています。最後まで読むと、VPNのセキュリティをよく理解できますので、企業のセキュリティ対策に役立ててください。

サイバーセキュリティ
ネットワークセキュリティとは?リスクと取るべき対策まとめ
本記事ではネットワークセキュリティについて解説しています。ネットワークセキュリティのリスクや事例、必要な対策を詳しく説明しています。企業に欠かせないセキュリティ対策がよく理解できますので、最後まで読んで参考にしてください。

サイバーセキュリティ
マルウェア対策とは?感染の脅威と対処法を事例や感染経路とともに解説!
この記事では、マルウェアの定義、脅威、感染経路、予防対策、感染後の対処法について解説しています。マルウェアはウイルス、トロイの木馬、スパイウェアなどを含み、個人情報の盗難やシステム破壊を目的としています。感染経路は多岐にわたり、予防にはソフトウェアの更新、セキュリティソフトの導入、不審なメールの回避などが必要です。感染後はネットワークの遮断とマルウェアの駆除、データの復旧などが重要です。

サイバーセキュリティ
身代金要求型ウイルス(ランサムウェア)の手口とは?データを守るための対策も紹介!
ランサムウェアとは身代金要求型のウイルスのことを指し、世界中で深刻な被害をもたらしています。その攻撃手口も巧妙化しており包括的なセキュリティ対策が求められます。この記事では、身代金要求型不正プログラムといわれるランサムウェアの概要、感染経路、手口や対策を詳しく説明します。

サイバーセキュリティ
ランサムウェアに感染したらどうする?感染経路と予防法や感染後の対処法を解説!
ランサムウェアの基礎知識と感染による被害、感染経路や予防策、感染したら行う対処法と禁止事項を具体的に解説します。ランサムウェアに感染したら被る金銭被害や業務停止、情報漏えいなどのリスクを回避するために必要なセキュリティ対策や教育など役立つ情報を提供します。

サイバーセキュリティ
マルウェアとランサムウェアの違いとは?特徴や感染経路と対策について解説!
ランサムウェアはマルウェアの一種であり、近年、ランサムウェアを含むマルウェアの被害が増加しています。企業や組織をマルウェアから守るためには、その特徴や対策を正しく理解することが重要です。 そこで本記事では、それぞれの違いや特徴、感染経路、対策を解説します。
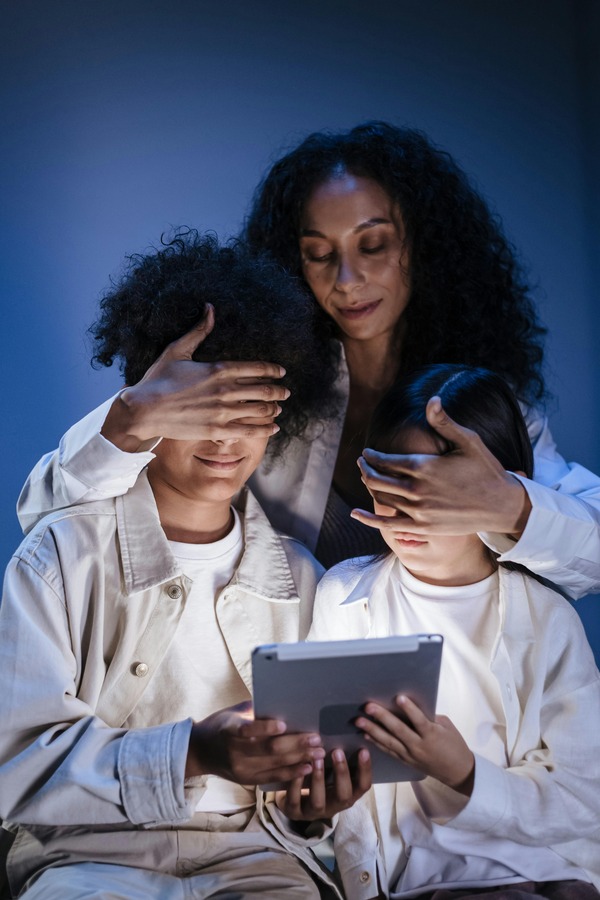
サイバーセキュリティ
ソーシャルエンジニアリングの手口とは?特徴や対策と被害事例を解説!
ソーシャルエンジニアリングとは、人間の心理的な隙を突くサイバー攻撃です。本記事ではソーシャルエンジニアリングの特徴や手口について解説します。実際に起きた事例も紹介するので、ソーシャルエンジニアリングの対策に役立ててください。
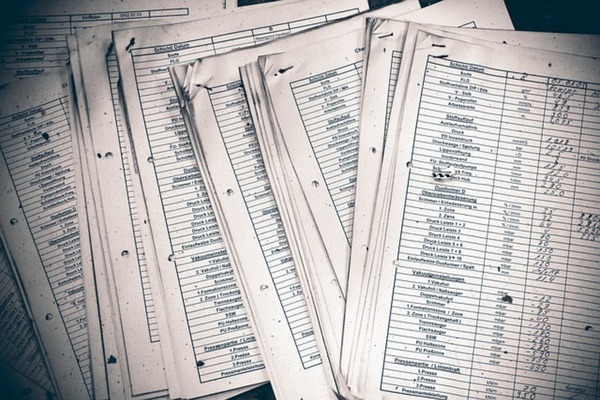
サイバーセキュリティ
ホワイトリストとは?対策の仕組みやセキュリティのメリットを解説!
ホワイトリストとは、安全と評価したWebサイトやIPアドレス等を定義したリストです。ホワイトリストに登録しているアプリケーションや通信のみ実行を許可します。ホワイトリストに登録していないものは全てブロックするため、高いレベルのセキュリティ対策となります。































