Magazine
Quantsマガジン
プロジェクト管理の手法13選!特徴や目的と活用方法を徹底解説!
プロジェクト管理とは、限られた時間や予算などのリソースの中で、様々な要素を統合的に管理し、効率的にプロジェクトを進行させる一連の活動を指します。今回はプロジェクト管理手法の特徴や活用の仕方、目的なども解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
プロジェクト管理の手法13選!
プロジェクト管理とは、限られた時間や予算などのリソースの中で、プロジェクトを成功に導くための計画、スケジュールやリスク管理、ステークホルダーとの調整、など様々な要素を統合的に管理し、効率的にプロジェクトを進行させる一連の活動を指します。
プロジェクト管理の要は「見える化」と「調整力」にあり、WBSやガントチャートといったツールを使って全体像を明確にし、ゴールに向けて関係各者全員を成功に導くのがプロジェクトマネージャーの役割です。ここではプロジェクト管理の手法を具体的に解説します。
1.PMBOK
PMBOK(Project Management Body of Knowledge)とは、米国プロジェクトマネジメント協会(PMI)が発行するプロジェクトマネジメントの国際標準です。プロジェクトのサイクル全体を網羅した包括的なガイドラインであり、世界中のプロジェクトリーダーに広く活用されています。
1987年に初めて発行され、今日まで活用されている、体系的にまとめられたプロジェクト管理やプロジェクトマネジメントのガイドラインです。
特徴と目的
PMBOKではプロジェクト管理のノウハウが5つのプロセス(立上げ、計画、実行、監視と管理、終結)と10つの知識エリア(統合、スコープ、スケジュール、コスト、品質、資源、コミュニケーション、リスク、調達、ステークホルダー)に分類され、定義されています。
QCD(品質、費用、納期)を管理し、プロジェクトの進行において「可能な限り高品質、低コスト、短納期」を目標に掲げ、実現するための計画を立案し、プロジェクトを成功に導くことが、PMBOKの目的です。
メリット・デメリット
PMBOKのメリットは、プロジェクト管理に関する共通の用語や手法を定義し、体系的に知識をまとめたことにあります。国際基準となっているため、世界中のグローバル企業で活用できます。
PMBOKのデメリットは、体系的に知識が網羅されている反面、複雑になっており習得するまでに時間がかかる点です。また柔軟性に欠ける点もあり、中規模以下のプロジェクトでは、個別最適されず、適さない場合もあります。
2.WBS
WBS(Work Breakdown Structure)とは、日本語で「作業分解構成図」と訳されます。プロジェクトの全体像を断層的に分解し、管理する手法です。最上位に成果物を置き、それを達成するために必要な作業を順次、下位レベルに分解していきます。
プロジェクト全体を可視化することで、各タスクの作業手順、関係性が把握しやすくなり、効率的にプロジェクトを進行できます。
特徴と目的
WBSを用いたプロジェクト管理では、必要な作業や成果物を全て洗い出し、一覧表にまとめます。縦軸に作業内容、横軸に担当者、工数見積もり、その成果実績、開始日と完了日などが記載されているのが一般的です。
WBSを活用する目的は、メンバー全員で、プロジェクトの全体像を目視確認することです。作業単位もしくは成果物単位で確認できるので、プロジェクトメンバーは安心して、進捗の把握ができます。
メリット・デメリット
WBSのメリットは、プロジェクトの全体像を把握できる点にあります。タスクの進捗管理が容易になり、遅延の早期発見やリソースの割り当てなどに役立ちます。断層的にプロジェクトを分解するので、作業レイヤーごとの責任者を明確にしやすく、責任の所在をわかりやすくできます。
WBSのデメリットは、プロジェクト規模が大きくなるに比例して、作成が困難になる点です。時間をかけて作成したが複雑になりすぎて、プロジェクト内容に変更がしにくくなるケースもあります。
3.CCPM
CCPM(Critical Chain Project Management)とは、各タスクの予備時間(バッファ)を一元管理し、納期遅延の可能性を最小限に抑える為の手法です。
Critical Chainとは、最も長く時間がかかると想定されるタスクを指します。CCPMを活用すると、Critical Chainの特定が速くなり、納期を守りやすくなります。
特徴と目的
CCPMでは、Critical Chainに着目し、タスクの優先順位を明確にし、予備時間の調整を行います。例えば、プロジェクト期間が60日、タスクの工程が6つあるとします。当初は工程1つに10日間を費やす予定だったのを、9日間に短縮すると、全体として6日間の余裕(バッファ)を持たせられます。万が一Critical Chainに労力を割かなければならなくなった場合に、そのバッファを割り当てられます。
CCPMは、納期遅延の可能性を抑えることが目的です。どのタスクも一定の予備時間が設けられているはずですが、その予備時間は浪費してしまいがちです。各タスクの余分なバッファを取り除き、余裕時間があるための心理的な作業の遅延を阻止できます。
メリット・デメリット
CCPMのメリットは、スケジュールを可視化でき、作業の優先順位を判断しやすくなる点にあります。各スケジュールが視覚化され、誰が何をいつまでにすべきかがはっきりするため、メンバーの意識も高まります。また、遅れが生じても、その影響を即座に把握できるので、迅速な対応が可能です。
CCPMのデメリットは、チームの協力体制が不可欠な点です。部門間の壁が高いと機能しません。さらに、短期プロジェクトには適さない傾向があります。タスクごとの余裕時間が少ない短期案件では、CCPMの真価を発揮しづらいのです。
4.PERT
PERT(Program Evaluation and Review Techniqu)とは、プロジェクトの各タスクの依存関係を明確にし、プロジェクトの流れを図示化する管理手法です。
各タスクの作業量や必要時間、作業手順などが明確にわかるため、プロジェクトメンバーは重要なタスクを把握でき、タスクの優先順位を意識しながら着手できます。
特徴と目的
PERTは、PERT図というタスクのネットワーク図を用いて、プロジェクトを管理します。各タスクをボックスで表現し、矢印で相互関係を明記します。タスクボックスの中に作業の手順や所要時間、納期などの情報を付加させる場合もあります。
PERTは、プロジェクト全体の流れを把握し、視覚的にスケジュールを管理する目的で活用されます。プロジェクトメンバー全員で、プロジェクトの流れを理解しながら進められるので、進捗の管理がしやすくなり、問題が発生しても早急に対応できます。
メリット・デメリット
PERTのメリットは、各タスクの所要時間や作業手順が視覚的に把握しやすいので、現実的なスケジュールを組み立てられる点です。また作業に時間のかかるタスクを予想できるので、メンバー同士での協力体制にも役立てられます。
PERTのデメリットは、プロジェクトの進捗状況を管理できない点です。あくまでもプロジェクト全体における各タスクの関係図を作成する管理手法ですので、進捗の進度は別のツールで把握する必要があります。
5.P2M
P2M(Project & Program Management)とは、PMBOKをベースに作られた日本発のプロジェクト管理手法です。「プログラム」という概念を導入し、複数のプロジェクトを統合的に管理します。
2001年に発行されたガイドラインで、2002年以降、日本プロジェクトマネジメント協会(PMAJ)により普及活動がなされています。
特徴と目的
PMBOKなどで整理されたプロジェクトマネジメントの手法は、一つのプロジェクトの成功に焦点を当てるのに対し、P2Mは、大規模プロジェクトのような複数のプロジェクトが関係しあっている場合にも、対応できる日本発の管理標準です。
その目的は、様々な企業やプロジェクトが複合的に関係しあっている、より大規模なプロジェクトをマネジメントするためです。プラントなどのエンジニアリング業界では、発電所や浄水場など様々な企業や業界が関わります。一つのプロジェクトの管理に適したPMBOKでは、不十分であったというわけです。
メリット・デメリット
P2Mのメリットは、PMBOKの課題である複合プロジェクトの統括管理に対応できる点です。米国発祥のPMBOKも第7班でプログラムの概念を取り入れたりと、P2Mを意識した改訂がなされています。プロジェクト管理のブラッシュアップがなされている点で、P2Mの意義は高いと言えます。
P2Mのデメリットは、その認知度にあります。P2Mは現在、日本のエンジニアリング業界で主に普及しているプロジェクト管理手法ですが、まだまだ広く活用されていないのが現状です。PMBOKのような世界標準になるには、さらなる普及活動が必要と言えます。
6.ガントチャート
ガントチャートとは、タスクの開始日、終了日、期間、進捗状況などを横棒グラフで表示するプロジェクト管理手法です。プロジェクト全体の進捗状況を視覚的に把握し、タスク間の依存関係を明確にすることで、プロジェクトの計画、管理、実行を効率化します。
タスクを視覚的に整理できるので、スケジュール全体を直感的に把握できます。
特徴と目的
ガントチャートでは、縦軸にタスク、横軸に日時を記載し、横棒グラフ的に表現するのが一般的です。どのタスクにどの程度の時間がかかるのか、が視覚的に確認が取れるので、工数の見積りや進捗確認がしやすいです。
プロジェクト全体を管理できるガントチャートから、チーム向けのガントチャート、個人向けのガントチャートと、徐々に落とし込んでいくと、隅々まで詳細に管理できる表を作成できるのも特徴です。
メリット・デメリット
ガントチャートのメリットは、スケジュールの妥当性をプロジェクトチーム全員で確認できる点です。情報交換が活発になり、タスク優先度に応じたリソースの割り当てなども比較的容易になります。
ガントチャートのデメリットは、柔軟性に欠ける点です。プロジェクト内容は進行途中で変更になるケースも多々あります。一度作成したガントチャートを更新するのは、手間がかかります。更新されるまで関係各者はプロジェクトの進捗確認ができなくなってしまいます。
7.PPM
PPM(Project Portfolio Management)とは、個々のプロジェクトだけでなく、ポートフォリオ全体の戦略と目標に基づいてプロジェクトを管理する手法です。限られたリソースを効率的に配分し、ポートフォリオ全体の価値を最大化することを目指します。
企業の展開する商品や事業の、市場の成長率や占有率を分析し、市場全体を俯瞰して、資金や人的リソースの戦略的投資を行います。
特徴と目的
PPMでは、事業分析をする際に、市場成長率と市場占有率の2軸を設定し、事業を4つの象限に分類します。PPMによる4つの象限とは以下の通りです。
- 売り上げが伸びやすい「花形」
- 成長見込みのある「問題児」
- 収益を生み出せない「負け犬」
- 多くの利益を生む「金のなる木」
「花形」は市場成長率、市場占有率ともに高く、売り上げが伸びやすい一方で、競合他社が多数存在し、価格競争などにより利益を産みにくいです。逆に市場成長率も占有率も低い状態を「負け犬」と言います。撤退や売却を検討し、余剰資金を生み出すことに専念すべきでしょう。
「問題児」は市場成長率は高く、市場占有率が低い状態を指し、「花形」へ昇華できる可能性を秘めています。市場成長率が低く、占有率が高い状態を「お金のなる木」と表現します。新規参入の企業が少ないため、積極的な投資が不要で、高い利益を生み出しやすい状態です。
メリット・デメリット
PPMのメリットは、自社の事業の市場でのポジションがどこにあるのかを分析することで、限られたリソースを効率的に分配できる点です。事業失敗のリスクが減り、事業の安定化を図れます。
PPMのデメリットは、単体事業の分析しかできない点です。複数の事業を展開している場合、各々の事業の相乗効果などを考慮しての分析が困難です。またPPMは市場成長率と占有率の2軸で分析するため、新規事業の分析には向いていません。新規事業が、どの程度市場のシェアを獲得するか、プロジェクト始動時点では分からないためです。
8.QFD
QFD(Quality Function Deployment)とは、日本発祥の製品開発手法です。「品質機能展開」と日本語訳され、顧客ニーズを軸に製品開発を進めます。
顧客ニーズを明確にし、そのニーズを製品・サービスの具体的な設計要件に落とし込むことで、顧客満足度を高めることを目指し、顧客が本当に求める製品・サービスを生み出す手法です。
特徴と目的
QFDでは、顧客の顕在ニーズに留まらず、未だ気付かれていない潜在ニーズまで掘り下げて分析します。顧客ニーズの分析を起点として、製品やサービスの開発における優先課題を見通します。
手戻りの少ない効率的な開発設計、および魅力的で差別化できた製品を産み出すことを目的に、1960年代に日本で生まれました。1980年代にはアメリカの自動車業界でも浸透するようになり、現在では世界中で実施されている製品開発手法です。
メリット・デメリット
QFDは、顧客ニーズの要求する品質、品質特例を正確に把握でき、開発課題として優先すべき事項と制約すべき事項を明確にするので、プロジェクトメンバーとの開発の方針を合わせやすく、効率的に進行できます。
デメリットとしては、製品の品質表の作成に時間がかかる点です。顧客ニーズの情報収集と分析に時間がかかる上、品質表に記載される情報量は膨大になる傾向にあります。
9.カンバン
カンバン(kanban)とは、1960年代にトヨタ自動車により開発された生産管理手法です。当時のアメリカで自動車産業では、MRPという手法が主流でしたが、トヨタ自動車の当時のエンジニアは、「自社では真似できない」と断念しました。
アメリカでの視察後、スーパーに立ち寄ったトヨタ自動車エンジニアの一行は、棚に陳列された商品を店員が見て周り、空きがあったら補充しているのを見つけます。スーパーの陳列方法を見て、これを製品開発に取り入れよう、と開発されたのがカンバン方式です。
特徴と目的
カンバンでは「仕掛けカンバン(生産指示カンバン)」と「引き取りカンバン」の2種類を使用します。仕掛けカンバンに指示された数の部品を製造し、仕掛けカンバンを取り付けた部品を工場の棚に置いておきます。担当者が、製造された部品を取りに行き、仕掛け看板を外し、代わりに引き取りカンバンを取り付けます。
引き取りカンバン付きの部品を、後工程の製造場所へ運び、部品を使用したら引き取りカンバンと仕掛けカンバンを入れ替え、前工程の棚へ戻します。カンバン方式は、部品の作りすぎや、余った部品の在庫の無駄を解消するために開発された管理手法です。
メリット・デメリット
カンバンは、目視できるカンバンを使用するシンプルな管理の仕組みで誰にでもわかりやすく、部品製造のリードタイムや消費スピードなどの知識がなくても、無駄なく効率よく製品管理や在庫管理を実施できるのがメリットです。
一方で、無駄な在庫を削減できる分、製造工程で障害が発生し、部品の欠品や不良品が発生した時の影響を受けやすいです。またカンバンの取り替え忘れや、カンバンの指示内容の変更が難しい点もデメリットと言えます。
10.スクラム
スクラムとは、アジャイル型開発手法の一つです。スクラムの由来は、ラグビースポーツのスクラムです。名前の通り、チーム一丸となって開発に取り組み進むことを目指しています。
プロジェクト管理の一つの手法なのですが、協調的なプロジェクト進行であったりプロセスよりも個人を重視している点で、アジャイル開発の手法と説明されることも多いです。
特徴と目的
スクラムは、1〜2週間程度の短期間のプロジェクトサイクルを繰り返します。その短いサイクルはスプリントと呼ばれます。10人以下でチームが結成され、各スプリントで具体的な目標を達成することで、プロジェクトを成功に導きます。
スクラムでは、プロジェクトマネージャーは存在せず、代わりにスクラムマスターがプロジェクトの進行役を務めます。スクラムマスターとプロジェクトマネージャーの違いは、意思決定や指示を行うか否かです。スクラムマスターは、意思決定はプロダクトオーナーに任せ、プロジェクトを円滑に進めるサポートに集中します。
メリット・デメリット
スクラムでは、意思決定を行うプロダクトオーナー、進行役のスクラムマスター、作業を進めるチームメンバーと役割が決められています。その為、プロジェクトの変更などにも柔軟に対応でき、必要に応じて計画を修正できます。
一方で、複雑なプロジェクトだとスプリントが複雑になり、全体像の進行を管理しにくくなる場合があります。高いチームワークが求められ、まとめ役であるスクラムマスターの負担が大きくなる傾向にあります。
11.スクラムばん
スクラムばんは、スクラムとカンバンを組み合わせた手法です。スクラムの短期間で成果を積み重ねるという特徴と、カンバンのタスク可視化とワークフロー改善という特徴を組み合わせることで、より効果的なプロジェクト管理を実現します。
スクラムばんは、スクラムの管理手法からカンバンへ移行(もしくはその逆)する際に進化した手法です。
特徴と目的
スクラムばんは、スクラムと同様に、短いサイクルのスプリントを使用します。同時にカンバンと同じ、個別タスクをプロジェクトの進行に組み込めます。スクラムとカンバンの機能をハイブリットに活用し、様々な規模のプロジェクトに柔軟に対応できます。
プロジェクトを小さなタスクに分解したいけど、視覚的にシンプルに進行させたい、という要望からスクラムばんは生まれました。
メリット・デメリット
スクラムばんの魅力は、スクラムとカンバンのいいとこ取りができる点です。スクラムの反復的な開発で全体の流れを作りつつ、カンバンで重要なタスクを目立たせられるので、柔軟かつ効率的に進められます。
ただし、この手法には課題もあります。新しい手法なため実績データが少なく、体系的なガイドラインもまだありません。そのため、チームごとに運用方法が異なり、標準化が難しいのが現状です。さらに、チームメンバーがスクラムとカンバンの両方を理解している必要があり、導入のハードルが高いのも事実です。
12.ウォーターフォール
ウォーターフォールとは、プロジェクトを複数の複数の工程に分け、上流工程から下流工程へ順番に終わらせていく管理手法です。要件が具体的に決定しているプロジェクトに適しています。
ウォーターフォールの名前の由来は、上流から下流へ水が流れる様子から来ています。
特徴と目的
ウォーターフォールは、古くからシステム開発や管理に活用されていました。システムの要件定義、設計、実装、テスト、運用と順序だって工程を進めていきます。
ウォーターフォールでは、前工程が終わらない限り、後工程は開始できません。また一度完了した工程はクローズするため、通り過ぎた工程に戻ることもありません。進捗の把握、進行の管理がしやすい手法ですが、修正が必要な際には手戻りが大きくなることが特徴です。
メリット・デメリット
ウォーターフォールの優れている点は、スケジュールの管理がしやすい点です。プロジェクト開始の段階で工数も確定しているため、人的リソースの割り当ても計画的に行えます。また綿密に計画を作成するので、成果物の品質を担保しやすいです。
一方で、途中で要件や仕様変更が入った際に、修正が困難になります。細部まで計画を作り込んでいるので、柔軟に変更できません。
13.アジャイル
アジャイルは、プロジェクトの工程を小さな単位で小分けにし、実装とテストを短いスパンで繰り返す管理手法です。この手法の特徴は、開発の各サイクルを短くすることで、変化への柔軟性を高めている点です。
クライアントのニーズを確認しながらブラッシュアップを重ねられ、仕様変更の対応力に優れています。最終の成果物がクライアントニーズに合致したものになりやすいです。
特徴と目的
アジャイルでは、各工程を1〜4週間単位の短いスパンに分割し、プロジェクトを進行させます。工程を小分けにしているため、クライアントからのフィードバックに対応しやすく、ニーズに応えながら、的確にプロジェクトを進行できます。
ただし、アジャイル管理は、プロジェクト管理の原則的な考え方の一つと捉えるのが適切だと言えます。アジャイル的な考え方と一緒に、前述の管理手法(スクラムやカンバンなど)を組み合わせるのが一般的です。
メリット・デメリット
アジャイルでは、各工程を小分けにしているので、仕様変更や障害が発生した場合でも手戻りが少なく済むのがメリットです。プロジェクトの計画段階で、仕様を細部まで決めないため、クライアントのニーズを反映しやすいです。
アジャイルには、スケジュール管理が複雑という側面もあります。複数のプロジェクトチームが小単位の開発を進めるため、全体像がわかりにくくなります。より良い製品を作ろうと、改善を繰り返しているうちに当初のプロジェクトの方向性から大きく脱線する可能性もあります。
プロジェクト管理の流れ
プロジェクト管理は、具体的にどのような流れで進んでいくのでしょうか。
ここでは、プロジェクト管理の基本的な流れを説明します。適切にプロジェクトを管理して、成功に導きましょう。
プロジェクトの目標の明確化
プロジェクトの計画が立ち上がったら、まずプロジェクトの目標を明確化しておきましょう。目標を明確にしておくことで、タスクの優先順位が決まり、どの工程にリソースを充填的に割くべきか定まります。タスクの洗い出しもでき、効率的な計画を立案できます。
またプロジェクトメンバーで目標を共有でき、共通認識を持てるのでモチベーション向上にも繋がります。
タスクの整理
プロジェクトの目標を明確にしプロジェクトメンバーで共有ができたら、目標達成のために、タスクの洗い出し、整理、優先順位付けを行いましょう。不要なタスクの排除もできます。
この際に、各タスクの担当者や処理期限も決めておきましょう。プロジェクトメンバーの能力や希望も踏まえて決定してあげると、よりスムーズにプロジェクトは進行します。
進捗の確認と修正
プロジェクトが開始されたら、進捗の確認はこまめに行いましょう。設定された処理期限に間に合いそうにないのなら、進捗のズレを修正するように対処しなければなりません。
例えば、余力のあるメンバーに追加支援を求めたり、優先順位の低いタスクの期限を延長したりといった方法があげられます。しかし、こうした修正を的確に行うには、チームとの日々のコミュニケーションが不可欠です。日頃から信頼関係を構築しておけば、遅れの初期段階で報告が入り、メンバーも協力的になるはずです。
プロジェクト管理手法の活用方法とポイント
プロジェクトを成功に導くには、プロジェクト管理手法の活用が不可欠です。その際に、どのような点に注意を払えばいいのでしょうか。
管理手法の活用方法とポイントを紹介します。
プロジェクトの目的の確認
プロジェクト管理手法を選ぶ際の第一歩は、プロジェクトの本質的な目的を明確にすることです。例えば新製品の開発なら、市場投入時期を重視するのか品質を最優先にするのか、その目標次第で最適な手法が変わってきます。
目的が定まれば、次はそれをチーム全体で共有し、手法の説明と理解を図ることが大切です。全員が同じ目線に立てば、手法の運用がスムーズになり、マネジメントも円滑に進められるはずです。目的の再確認は、プロジェクトの節目ごとに行うと効果的でしょう。
工程の細分化
プロジェクトを効果的に管理するには、タスクや工程を細かく分割することが重要なポイントです。これにより、業務量の全体像を把握しやすくなり、完了までの流れを視覚化できます。
ただし、極端に細分化しすぎると、かえって全体が見づらくなったり、管理が複雑になりすぎる恐れがあります。適切な粒度を見極めるとともに、各工程の依存関係も整理しておく必要があります。こうした準備が整えば、プロジェクトの性質に合った最適な管理手法を選択しやすくなるはずです。
リソースの確保
プロジェクトをスムーズに進行させるには、リソースの確保は不可欠です。人材、設備、予算など、プロジェクトに必要なリソースを事前に十分確保します。
リソースが確保できたら、次はそれに合わせて最適な管理手法を選びます。人員が限られていれば、スリムな手法を採用し、予算に余裕があれば、高機能なツールの導入も検討できるでしょう。このように、リソースの状況次第で柔軟に手法を使い分けることが賢明です。
チームメンバーのモチベーションの向上
プロジェクトを円滑に進めるうえで、メンバーのモチベーション維持は極めて重要です。意欲の低下は作業効率を著しく低下させ、進捗の大幅な遅れにつながりかねません。
プロジェクトリーダーは、メンバーとコミュニケーションを密に取り、適切な指導やフィードバックを心がける必要があります。メンバーとの信頼関係の構築がプロジェクトの成功の鍵を握ります。プロジェクトメンバーとコミュニケーションが取りやすい管理手法を選びましょう。
情報の共有
プロジェクトを成功に導くためには、チームメンバー間での円滑な情報共有が欠かせません。進捗状況を随時共有し合えば、いざ遅れが生じた際にも、すぐに対策を講じられます。
情報共有を積極的に行えば、作業の属人化リスクも低減できます。情報が適切に共有されていれば、問題発生時に他のメンバーがスムーズにフォローに入れます。コミュニケーションを促進する管理手法の選択が重要となります。
チームメンバーとの信頼関係の構築
プロジェクトの成功には、高度な管理手法を使うことと並んで、チームメンバーとの信頼関係の構築が極めて重要です。いくら優れた手法を導入しても、メンバーとの協力体制が整っていなければ、適切に運用できる訳がありません。
そのため、プロジェクトの立ち上げ時から、手法の理解を深めてもらうとともに、お互いを信頼し合える関係性を築いていくことが不可欠です。メンバー一人ひとりが手法の意義を理解し、積極的に活用する意識を持てるよう、リーダーは丁寧な方針説明と信頼構築に努めましょう。
リスク対策
プロジェクトを遂行する上で、何らかの問題やリスクが発生するのは避けられません。計画の遅延や人員の変更、資金の不足など、様々な事態に備えておく必要があります。
そこでリスク対策を事前に立てることが重要となります。CCPMのようにバッファを設けるなど、トラブル発生時の余裕を作っておけば、スムーズな進行が可能になります。リスク発生を前提としたうえで、臨機応変に対応できる管理手法を選ぶことが賢明でしょう。
プロジェクト管理ツールの導入
プロジェクト管理では、適切なツールの選定が重要なポイントの一つです。作業の実態に合わないツールを使うと、かえって非効率になりかねません。
一般的には、ExcelやGoogleスプレッドシートのような柔軟性の高い汎用ツールが活用されることが多いでしょう。ただし、ツールは手段に過ぎず、プロジェクトの進捗を視覚化し、効率的に管理できるかどうかが本質的に重要です。手作業でもいいので、メリハリのある進捗管理ができれば十分です。
おすすめのプロジェクト管理ツール
プロジェクト管理には様々なツールが存在し、適切なものを選ぶことが肝心です。チームの特性やプロジェクトの性質に合わせて、使い勝手の良いツールを取り入れましょう。
ここでは4つのおすすめツールを紹介します。自社のニーズを分析したうえで、最適なツールを選び、効率的なプロジェクト運営を実現してください。
OBPM Neo
OBPM Neoとは、PMBOKに準拠した総合型プロジェクト管理ツールです。機能面に優れ、プロジェクト管理に必要なプロセスを網羅的に管理できます。
情報は全てクラウドデータベースに格納されるので、メンバー全員がリアルタイムで情報を確認・共有できます。このように、進捗の「見える化」が容易なのが大きな利点です。適切な情報共有がスムーズに行えるため、効率的にプロジェクトが進行します。
Asana
Asanaは、プロジェクトやタスクを一元管理できるツールで、UIメニュー画面がわかりやすく設計されています。複雑な操作が不要で、直感的に使用できる点が魅力です。
Asanaの強みは他のクラウドサービスとの連携性にもあります。例えばGmailやGoogleドライブ、Dropboxなどと簡単に連携でき、スムーズなタスク管理が可能です。多様なクラウドツールを組み合わせて利用したい場合は、Asanaが適切な選択肢と言えるでしょう。
TimeTracker NX
TimeTracker NXは、専門知識がなくてもプロジェクト管理ができる手軽さが最大の魅力です。工数入力はシンプルなドラッグ&ドロップ操作で行え、スケジュール計画も直感的におこなえます。
また、進捗状況や課題、不具合などがビジュアルで一目瞭然です。プロジェクトの全体像を把握しやすく、現場レベルでも管理が容易なのが特長です。管理者目線でなく、作業者側に立った使いやすさが評価できるツールといえるでしょう。
Redmine
Redmineは、オープンソースで無料で利用できるプロジェクト管理ツールです。タスクを「チケット」に登録するだけで、ガントチャートなどが自動生成されるので、手間なくプロジェクト管理を始められます。
Redmineの最大の魅力は、プラグインが多数公開されているため、用途に合わせてカスタマイズが可能な点です。一方で、基本的にはサポート体制がないため、プラグインの導入や設定に知識がないと、活用が難しいです。
目的に合ったプロジェクト管理手法を選択しよう
本記事では、プロジェクト管理の具体的な手法、流れ、管理手法の活用方法やポイントについて解説してきました。
プロジェクト管理手法は、一つひとつに特徴があり、向き不向きがあります。大切なのは、プロジェクトの性質や目的に合った手法を選ぶことです。いずれの手法を選んでも、形式的な適用に陥らないことが重要です。
プロジェクトの目的を明確にし、自社のプロジェクトのニーズに合った、管理手法を選択しましょう。本記事の内容を参考にして、ぜひプロジェクトを成功に導いてください。
コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング
コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。
クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由
②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供
③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス
クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事

PMO
プロジェクトリーダー(PL)の役割とは?PMとの違いと4つの仕事内容を解説
プロジェクトリーダー(PL)の役割とは何か、PMとの明確な違いと具体的な4つの仕事内容を解説。現場のチームを率いるPLに求められる必須スキルや、その重要性についてもわかりやすく説明します。

PMO
プロジェクトリーダー(PL)とは?PMとの違い・役割・必要なスキルを解説
プロジェクトリーダー(PL)とは何か、その役割やPMとの明確な違いを徹底解説。具体的な仕事内容から、PLに求められる3つの必須スキル、そしてSEからのキャリアパスまで、現場のリーダーを目指すすべての方に必要な情報を網羅します。

PMO
SEとPMの違いとは?仕事内容・スキル・年収を徹底比較【キャリアパスも解説】
SEとPMの違いを、仕事内容、必要なスキル、年収、責任範囲など5つの軸で徹底比較。SEからPMを目指すための具体的なキャリアパスや、求められるスキルの転換についても詳しく解説します。

PMO
認定スクラムマスター(CSM®)とは?取得方法・費用・難易度まで徹底解説
認定スクラムマスター(CSM®)とは何か、その価値と具体的な取得方法を徹底解説。必須となる研修内容から費用、試験の難易度、資格の更新方法まで網羅し、PSM™との違いも紹介します。

PMO
スクラムマスターの役割とは?仕事内容と3つの支援対象をスクラムガイドに基づき解説
スクラムマスターの役割と仕事内容を、公式ルールブックであるスクラムガイドに基づき徹底解説。開発者、プロダクトオーナー、組織という3つの支援対象への具体的な関わり方を紹介します。

PMO
スクラムマスターのおすすめ資格3選|CSMとPSMの違いを徹底比較【2025年最新】
スクラムマスターに関するおすすめの資格を徹底解説。世界的な二大資格であるCSM®とPSM™の違いを8つの軸で比較して紹介します。

PMO
プロダクトマネージャー(PdM)とは?仕事内容・役割からなり方まで解説
プロダクトマネージャー(PdM)とは何か、その仕事内容や役割、プロジェクトマネージャー(PM)との違いを初心者にもわかりやすく解説します。

PMO
テックリードとは?役割や仕事内容、エンジニアリングマネージャーとの違いを解説
テックリードとは何か、その役割や仕事内容、そしてエンジニアリングマネージャー(EM)との明確な違いを解説します。求められるスキルから、テックリードになるためのキャリアパスまで、現代の開発チームに不可欠なこの役割の全てがわかります。
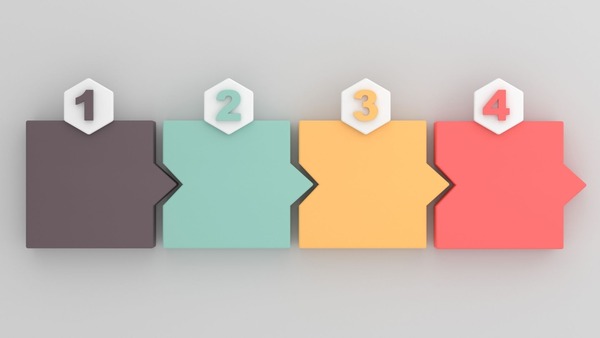
PMO
ロードマップとは?作り方の5ステップと種類別のテンプレート
ロードマップの正しい意味と作り方を解説。プロジェクト計画(ガントチャート)との明確な違いから、作成する目的、具体的な5つのステップ、種類別のテンプレートまで網羅的に紹介します。

PMO
ITプロジェクト管理とは?成功に導く5つのコツとおすすめツールを解説
ITプロジェクトがなぜ難しいのか、その理由から、成功に導く5つの具体的なコツ、そして開発手法の選び方やおすすめの管理ツールまで、専門家が分かりやすく解説します。































