Magazine
Quantsマガジン
ホワイトリストとは?対策の仕組みやセキュリティのメリットを解説!
ホワイトリストとは、安全と評価したWebサイトやIPアドレス等を定義したリストです。ホワイトリストに登録しているアプリケーションや通信のみ実行を許可します。ホワイトリストに登録していないものは全てブロックするため、高いレベルのセキュリティ対策となります。
ホワイトリストとは
ホワイトリストとは、安全と評価した対象をまとめたリストです。ホワイトリストに登録されたアプリケーションやIPアドレスを許可し、登録されていない場合はブロックする仕組みです。ホワイトリストには、主に以下の内容が登録され、フィルタリングの判断材料となります。
- IPアドレス
- Webサイト
- アプリケーション
- メールアドレス
- 電話番号
一方、ホワイトリストとは別にブラックリストもあります。近年はセキュリティ対策として、ホワイトリストを採用するケースが多くなりましたが、ブラックリストを採用する場合もあります。
ここではホワイトリストの詳細、ブラックリストとの違い、ホワイトリスト方式のメリット、デメリットを見ていきましょう。
ホワイトリストとブラックリストの違い
ホワイトリストとブラックリストは、どちらもメリットとデメリットがあり、一方が優れているということはありません。いずれを採用するかは、個々の事情に合わせて選択する必要があります。
セキュリティへの対策として考えた場合、安全と評価した相手のみを許可するホワイトリストの方が、一般的にセキュリティが高くなります。
ブラックリストとは
ブラックリストとは、危険と評価した対象をまとめたリストです。ブラックリストに載ったアプリケーションやIPアドレス等をブロックする方式を、「ブラックリスト方式」と呼びます。
サイバー攻撃で利用されるC&Cサーバや、フィッシングサイトが主なブラックリストの登録対象です。C&Cサーバやフィッシングサイトは日々増え続けているため、信頼できるセキュリティベンダーが提供するリストを自動的に取り込み、常に最新のブラックリストを維持する必要があります。
ただし、未知のC&Cサーバやフィッシングサイトはセキュリティベンダーも把握できないため、ブラックリストに登録されず、ブロックできない恐れがあります。
ブラックリストとホワイトリストの違い
ブラックリストとホワイトリストの違いは、安全と評価できる対象か否かの違いです。セキュリティ対策としては、ブラックリスト方式が通信を拒否する対象を管理する仕組みに対して、ホワイトリスト方式は通信を許可する対象を管理する仕組みになります。
例えば社内システムのように社内と支所からのみアクセスされる場合は、ホワイトリスト方式を使います。これは社内と支所が安全と評価できるためであり、それ以外は全て安全ではないと識別できるためです。一方、ECサイトのように不特定多数からアクセスされる場合は、相手が安全かどうか評価できないため、ブラックリスト方式を用います。
ただし、社内からの内部不正は見抜けません。ホワイトリスト方式を採用しているからと言っても、万全ではありません。
ホワイトリスト方式の仕組み
ホワイトリスト方式の仕組みは、通信やアプリケーションが起動するたびにホワイトリストを参照し、ホワイトリストに載っていれば実行を許可、載っていなければブロックします。リストに載っていない対象は、一切起動しないことで安全性を確保する方式です。
ホワイトリスト方式の例として、子供向け携帯電話があります。子供向け携帯電話は、連絡先に登録した電話番号しか通話できません。子供向け携帯電話は、不審な電話番号からの着信がないホワイトリスト方式の方が安全といえます。
ホワイトリストのメリット
ホワイトリストは安全と評価した対象のみを取り扱うため、一般的にブラックリスト方式に比べてセキュリティが高くなります。その他にもホワイトリストの採用で様々なメリットがあります。ここでは、具体的なメリットを見ていきましょう。
メリット1:更新頻度が少なくすむ
メリットの1つは、リストの更新頻度が少なくすむ点が挙げられます。ホワイトリストは安全と評価した対象のみを登録するため、新たなマルウェアやフィッシングサイトが生じたとしても、ホワイトリストへの登録は不要です。そのため日々更新していく必要がなく、更新頻度が少なくすみます。
またウィルス対策ソフトのように、パターンの更新といった日々のメンテナンスが必要ありません。そのため、インターネットを利用しない閉じたネットワークでも運用が可能です。
メリット2:事前知識が不要
メリットの2つ目は、事前知識が不要という点が挙げられます。これは新たなマルウェアが発生したとしても、ホワイトリストに登録しなければ、攻撃者によるマルウェアの実行をブロックできるためです。つまり新たな脅威に対抗するための調査や、対策といった事前知識が不要です。
メリット3:無許可のものはブロック
メリットの3つ目は、無許可のものはブロックするという点が挙げられます。例えば、ユーザが無許可でアプリケーションをインストールしても、ホワイトリストに登録されていないため、アプリケーションはブロックされます。同様に、許可されていないWebサイトやサービスもブロックされます。無許可のものをブロックするという動きは、セキュリティ対策として非常に大きなメリットです。
メリット4:総合的にセキュリティ力が高い
メリットの4つ目は、総合的にセキュリティ力が高い点です。動作の対象を安全と評価できる相手に絞り込むため、安全性が高くなります。ホワイトリストに登録しない限り、メリット2にあるように、攻撃者による新たなマルウェアの実行をブロックしたり、メリット3にあるように、無許可のアプリケーションをブロックしたりできます。そのため、総合的にセキュリティ力が高いといえます。
ホワイトリストのデメリット
ホワイトリストにはデメリットも存在します。ホワイトリストのデメリットを理解し、対策を講じなければ、強度の高いセキュリティ対策を維持できなくなります。高いセキュリティレベルを維持するために、ホワイトリストのデメリットを見ていきましょう。
デメリット1:過検知・誤検知
デメリットの1つ目は、過検知・誤検知を起こす点です。ホワイトリストの前提は、あらかじめ許可する対象を登録することです。そのため、新たなサービスを導入する際に、ホワイトリストに全て登録する必要があります。登録が漏れると、誤検知を起こし必要なサービスが利用できません。
例えば、クラウドサービスへの許可をホワイトリスト方式にした場合です。新たなクラウドサービスを追加するたびに、ホワイトリストに追加登録が必要です。登録が漏れた場合は、必要な業務が行えず機会の損失を招く結果になりかねません。
また、今まで利用していたサービスを解約する場合は、ホワイトリストから削除しなければなりません。ホワイトリストからの削除が漏れると、過検知を起こす原因になります。
デメリット2:定期的なリストの見直し
デメリットの2つ目は、定期的なリストの見直しが必要な点です。例えば、ホワイトリストを利用して、一部のパソコンにアクセスを許可している場合、パソコンが故障や更改などで入れ替わると、ホワイトリストも更新が必要になります。また、デメリット1と同様に、利用していたサービスを解約する場合は、ホワイトリストの削除が必要になります。
以上の理由により、ホワイトリストは定期的に見直しが必要です。
デメリット3:防御性と運用性の関係
デメリットの3つ目は、防御性と運用性の関係です。ホワイトリストは、許可する対象のみを登録して防御性を向上させています。一方、ホワイトリストを大量に登録すると、運用性は向上しますが、許可する対象が増えるため、防御性は低下します。つまり、防御性と運用性は相反する関係です。
近年のサービスは、複数のクラウドサービスを複合的に利用するシステムが多いため、ホワイトリストの登録対象も増加しています。ホワイトリストに登録したWebサイトやサービスが、マルウェアや不正なアクセスにより、汚染されるリスクも考慮が必要です。
ホワイトリストの拡大は、セキュリティホールも拡大させる要因になりえるという認識が必要です。そのため、防御性と運用性のバランスが重要となります。
デメリット4:リストの運用が煩雑
デメリットの4つ目は、リストの運用が煩雑な点です。ホワイトリストの作成は、許可する対象をリストアップしなければなりません。リストアップする手間と、リストアップした相手がホワイトリストに相応しいセキュリティ対策の仕組みを持っているかを、確認する必要があります。
また一時的にサービスやアプリケーションを利用したい場合、ホワイトリストに追加してもらう必要があります。一時的な利用が終わった後、すみやかにホワイトリストから削除する必要もあり、リストの運用が煩雑です。
デメリット5:定期的な監査が必要
デメリットの5つ目は、定期的な監査が必要な点です。例えば、相手企業が不正行為を行った場合や、マルウェアに感染した場合、事情を確認したうえで、ホワイトリストから削除するか否かを判断する必要があります。ただし、必ずしも相手先から報告があるとは限りません。そのため、定期的にホワイトリストの登録先を監査し、問題ないかの確認が必要です。
また、ホワイトリストを悪用した、内部の不正行為も考慮が必要です。不正行為が行われていないか、定期的なログの監査が重要です。
ホワイトリスト活用例
昨今のセキュリティ意識の向上にともない、ホワイトリストは広く利用されています。ブラックリストとの使い分けは必要ですが、ホワイトリストの活用で、より強度の高いセキュリティ対策が期待できます。ここでは、ホワイトリストの活用方法にはどのようなものがあるか見ていきましょう。
Webサイトのフィルタリング
ホワイトリストの活用法の1つに、Webサイトのフィルタリングがあります。例えば、生徒が授業中に必要のないWebサイトを閲覧しないように、認められたWebサイトのみに利用を制限する場合です。授業で利用するWebサイトのみを、ホワイトリストに登録します。
その他、企業がインターネットの利用を禁じつつ、特定のクラウドサービスを利用する場合です。この場合、ホワイトリストにはクラウドサービスのWebサイトを登録します。IPアドレスではなくWebサイトを登録する理由は、サービス提供元が仕様変更などでIPアドレスを変更する場合があるためです。Webサイトの登録であれば、IPアドレスが変更されても、ホワイトリストに影響がありません。
IPアドレス制限
ホワイトリストの活用例の1つに、IPアドレス制限があります。例えば、自社のホームページをクラウドで運用する場合です。ホワイトリストにIPアドレスを登録し、更新権限のみホワイトリストでフィルタリングします。すると、ホームページの参照はどこからでもできますが、更新作業は自社のみに限定できるため、改ざん防止に有効です。
その他、社内システムを持つ企業では、社内と支所のIPアドレスを登録し、それ以外はブロックする活用方法もあります。
ホワイトリストまとめ
ホワイトリストは、安全と評価できる対象のみを許可する方式のため、不正なアクセスが発生しにくい仕組みを持つ有効なセキュリティ対策です。デメリットへの対策は必要ですが、ホワイトリストのメリットを有効活用し、安全な環境を構築しましょう。
コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング
コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。
クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由
②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供
③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス
クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事

サイバーセキュリティ
マクロウイルスとは?オフィス製品に感染する仕組みと対策を解説!
マクロウイルスは、ビジネスに不可欠な「マイクロソフトオフィス」製品のマクロ機能を悪用するマルウェアの一種です。ここでは、マクロウイルスの特徴と感染経路や、具体的な種類と被害例、詳しい対策方法について解説します。感染の仕組みを理解して対策を講じましょう。

サイバーセキュリティ
サイバー攻撃とは?攻撃の目的・種類や手口と被害事例から対策を紹介!
サイバー攻撃とは、サーバやパソコンなどの機器に対して不正アクセスや情報窃取、破壊活動などを行う攻撃の総称です。近年はサイバー攻撃が高度化し、どんな組織もサイバー攻撃にあうリスクがあります。本記事では、サイバー攻撃の種類や手口、被害事例について詳しく解説します。
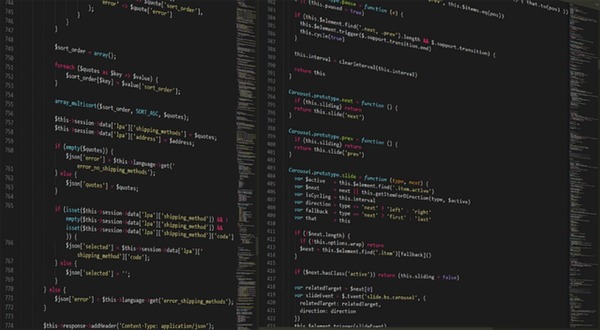
サイバーセキュリティ
VPNのセキュリティは安全?仕組みやメリットとリスクを解説!
本記事ではVPNのセキュリティについて解説しています。安全性と危険性、仕組み、メリット、さらにはリスクまで詳しく説明しています。最後まで読むと、VPNのセキュリティをよく理解できますので、企業のセキュリティ対策に役立ててください。

サイバーセキュリティ
ネットワークセキュリティとは?リスクと取るべき対策まとめ
本記事ではネットワークセキュリティについて解説しています。ネットワークセキュリティのリスクや事例、必要な対策を詳しく説明しています。企業に欠かせないセキュリティ対策がよく理解できますので、最後まで読んで参考にしてください。

サイバーセキュリティ
マルウェア対策とは?感染の脅威と対処法を事例や感染経路とともに解説!
この記事では、マルウェアの定義、脅威、感染経路、予防対策、感染後の対処法について解説しています。マルウェアはウイルス、トロイの木馬、スパイウェアなどを含み、個人情報の盗難やシステム破壊を目的としています。感染経路は多岐にわたり、予防にはソフトウェアの更新、セキュリティソフトの導入、不審なメールの回避などが必要です。感染後はネットワークの遮断とマルウェアの駆除、データの復旧などが重要です。

サイバーセキュリティ
身代金要求型ウイルス(ランサムウェア)の手口とは?データを守るための対策も紹介!
ランサムウェアとは身代金要求型のウイルスのことを指し、世界中で深刻な被害をもたらしています。その攻撃手口も巧妙化しており包括的なセキュリティ対策が求められます。この記事では、身代金要求型不正プログラムといわれるランサムウェアの概要、感染経路、手口や対策を詳しく説明します。

サイバーセキュリティ
ランサムウェアに感染したらどうする?感染経路と予防法や感染後の対処法を解説!
ランサムウェアの基礎知識と感染による被害、感染経路や予防策、感染したら行う対処法と禁止事項を具体的に解説します。ランサムウェアに感染したら被る金銭被害や業務停止、情報漏えいなどのリスクを回避するために必要なセキュリティ対策や教育など役立つ情報を提供します。

サイバーセキュリティ
マルウェアとランサムウェアの違いとは?特徴や感染経路と対策について解説!
ランサムウェアはマルウェアの一種であり、近年、ランサムウェアを含むマルウェアの被害が増加しています。企業や組織をマルウェアから守るためには、その特徴や対策を正しく理解することが重要です。 そこで本記事では、それぞれの違いや特徴、感染経路、対策を解説します。
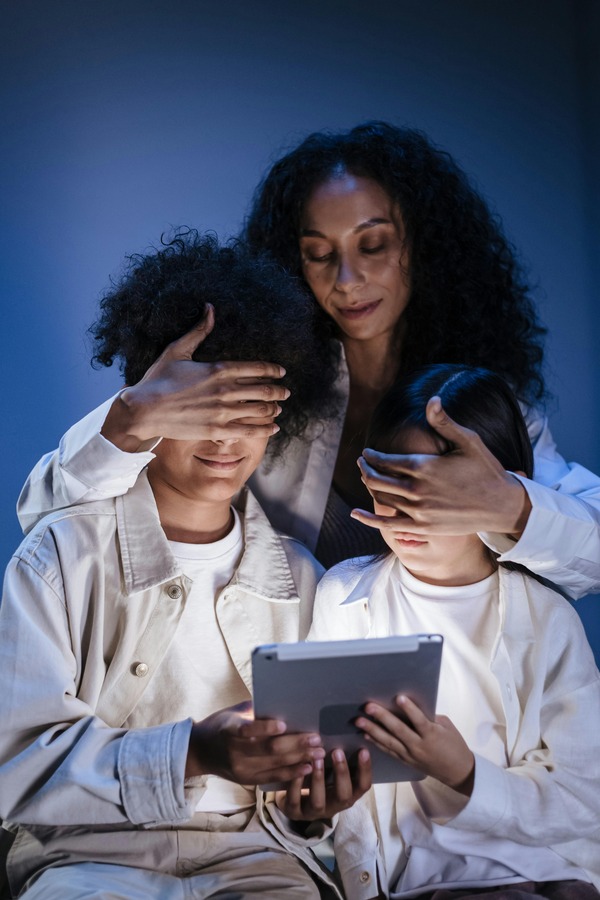
サイバーセキュリティ
ソーシャルエンジニアリングの手口とは?特徴や対策と被害事例を解説!
ソーシャルエンジニアリングとは、人間の心理的な隙を突くサイバー攻撃です。本記事ではソーシャルエンジニアリングの特徴や手口について解説します。実際に起きた事例も紹介するので、ソーシャルエンジニアリングの対策に役立ててください。

サイバーセキュリティ
脆弱性とは?意味や危険性と発生原因・対策を徹底解説!
脆弱性の意味は、システムにとって重大な危険性をもたらす設計上の欠陥や誤りです。近年、脆弱性が発見されるとすぐにサイバー攻撃に悪用されるケースも増えています。脆弱性を放置するリスクについて、事例をもとに原因を確認し、適切な対策を実施しましょう。































