Magazine
Quantsマガジン
セキュリティホールとは?脆弱性との違いやリスク・被害事例と対策方法を解説!
本記事では、セキュリティホールについて解説しています。セキュリティホールと脆弱性との違いやリスク、被害事例、さらに対策方法を詳しく説明しています。企業のセキュリティ対策の参考となりますので、ぜひ最後までご覧ください。
セキュリティホールとは?
セキュリティホールとは、例えるなら建物の窓やドアの鍵が壊れているようなもので、サイバー攻撃者がそこから侵入し、情報を盗んだりシステムを破壊したりする可能性があります。
ソフトウェアやOSを開発する際に、設計ミスやプログラムの不具合などが原因で生じるもので、いわばシステムの弱点です。放置すると、企業の機密情報漏洩やサービス停止など、取り返しのつかない事態を招く恐れがあります。
そのため、企業は常に最新のセキュリティ対策を講じ、システムの脆弱性をいち早く発見し、修正することが重要です。
セキュリティホールは、サイバー攻撃に対する防御の最前線であり、対策は企業の存続を左右すると言っても過言ではありません。
脆弱性との違い
セキュリティホールと脆弱性は、どちらもサイバー攻撃の脅威を表す言葉として混同されがちですが、実はその意味合いは異なります。
セキュリティホールは、サイバー攻撃者がそこから侵入するための具体的な経路です。システムやソフトウェアのプログラムミス(バグ)によって生じ、悪意ある攻撃者がその穴を悪用して、情報漏洩やシステム破壊などの被害が発生する可能性があります。
一方、脆弱性は、より広範な概念です。セキュリティホールも脆弱性の一種ですが、それ以外にも、セキュリティ対策の不備や人的ミスなど、システム全体のセキュリティレベルを低下させるさまざまな要因が含まれます。
例えば、従業員のセキュリティ意識の低さや、古いソフトウェアを使い続けているといった状況も、脆弱性と言えるでしょう。つまり、セキュリティホールは脆弱性の一つであり、脆弱性はセキュリティホールを含むより包括的な概念であると理解することが重要です。
企業は、セキュリティホールだけでなく、脆弱性全体を把握し、適切な対策を講じると、サイバー攻撃のリスクを最小限に抑えられます。
セキュリティホールによるリスク
セキュリティホールが存在すると、大きなトラブルを引き起こす可能性があります。具体的なリスクとして4つ挙げて、それぞれについて解説します。
マルウェア感染
コンピューターのセキュリティホールが放置されると、不正なコードが実行される危険性があります。結果として、コンピューターがマルウェアに感染し、情報漏えいなどの被害が発生するだけでなく、他のコンピューターへの感染が拡大する恐れもあります。
情報漏洩
マルウェア感染やハッキングにより、個人情報や機密情報が漏洩するリスクがあります。情報が一度漏洩すると、金銭被害やなりすまし、標的型攻撃など、さまざまな二次被害につながる可能性があります。
ハッキング
マルウェア感染により、コンピューターが遠隔操作されるリスクがあります。また、動作や処理が重くなる、突然シャットダウンする、自ら操作していないにもかかわらずWebカメラにアクセスされるなどの危険性もあります。
ゼロデイ攻撃
修正パッチがベンダーから提供される前に見つかるセキュリティホールは、ゼロデイ脆弱性と称されます。
このタイプの脆弱性をターゲットにした攻撃はゼロデイ攻撃として知られており、まだ対策が施されていない状態で実施されるため、非常に高いリスクで被害を受ける可能性があります。
特に多くの人が使用しているソフトウェアを対象としたゼロデイ攻撃は、広範囲にわたる重大な被害を引き起こすかもしれません。
セキュリティホールを狙う攻撃の種類
セキュリティホールを狙った攻撃は非常に脅威です。危険を回避するには、具体的な攻撃の手法やリスクについて理解しておかなければなりません。ここでは、攻撃の種類について紹介します。
SQLインジェクション
SQLインジェクションは、Webサイトのデータベースを標的にしたサイバー攻撃です。データベースとは、Webサイトが管理する顧客情報や商品情報などを保管する「情報倉庫」のようなものです。
攻撃者は、Webサイトの入力フォームなどに悪意のあるSQL文(データベースを操作するための命令文)を巧みに紛れ込ませ、データベースを不正に操作します。データベースに保管された個人情報やクレジットカード情報などを盗み出すことが可能です。
特に、顧客情報を大量に保有するECサイトや会員制Webサイトは、攻撃者にとって格好の標的です。日常的に利用するネットショッピングサイトで、個人情報が知らないうちに盗み出されているかもしれません。
SQLインジェクションによる情報漏洩は、企業の信頼を大きく損なうだけでなく、被害者である顧客にも深刻な影響を及ぼします。しかし、このような被害は氷山の一角に過ぎません。多くの企業がSQLインジェクションの脅威にさらされており、その対策は急務です。
Webサイトを運営する企業は、SQLインジェクションへの対策を徹底し、顧客情報をはじめとする重要な情報を守る責任があります。
OSコマンドインジェクション
OSコマンドインジェクションは、Webサイトを介してコンピューターを乗っ取る、危険なサイバー攻撃です。
攻撃者は、Webサイトの入力フォームなどに、OSを操作する命令を紛れ込ませます。Webサイトを通じて、まるで自分のコンピューターのように、標的のコンピューターを遠隔操作することが可能です。
もし攻撃が成功すれば、個人情報や企業秘密などの情報漏洩はもちろん、ファイルの改ざんや削除、さらにはウイルス感染といった深刻な被害が発生する可能性があります。
また、乗っ取られたコンピューターは、他のWebサイトへの攻撃の踏み台として利用される場合もあり、知らないうちに加害者になってしまう恐れもあります。
OSコマンドインジェクションは、まさにコンピューターを遠隔操作して犯罪に利用する、現代のサイバー犯罪の代表格と言えるでしょう。
被害を防ぐためには、Webサイトの設計段階から、外部からの不正な命令を受け付けない仕組みを組み込むのが重要です。
クロスサイトリクエストフォージェリ
クロスサイトリクエストフォージェリは、巧妙なサイバー攻撃です。攻撃者は、Webサイトの掲示板やお問い合わせフォームなどに、悪意のあるリンクやスクリプトを仕込みます。利用者がそのリンクをクリックしたり、ページを閲覧したりするだけで、攻撃者の意図する操作が実行されてしまうのです。
利用者のアカウントが乗っ取られたり、個人情報が漏洩したりするだけでなく、意図せずネットショッピングで商品を購入させられたり、SNSで不適切な投稿をさせられたりする危険性もあります。
利用者の意図を無視して、Webサイトを悪用する「なりすまし」攻撃であり、その被害は深刻です。
DNSキャッシュポイズニング
DNSキャッシュポイズニングは、インターネットの住所録であるDNSサーバーを改ざんし、ユーザーを偽のWebサイトへ誘導する巧妙なサイバー攻撃です。
DNSサーバーは、Webサイトの住所(ドメイン名)と電話番号(IPアドレス)を紐づける役割を担っています。攻撃者はこのDNSサーバーに侵入し、偽の情報を書き込むことで、ユーザーを偽のWebサイトへ誘導します。
偽のWebサイトは、本物のWebサイトと見分けがつかないほど精巧に作られている場合が多く、ユーザーは偽物と気づかずに個人情報を入力したり、マルウェアをダウンロードさせられたりする危険性があるのです。
DNSキャッシュポイズニングは、インターネットの信頼性を揺るがす深刻な脅威であり、個人情報漏洩や金銭被害など、さまざまな被害を引き起こす可能性があります。
クロスサイト・スクリプティング
クロスサイトスクリプティングは、Webサイトの入力フォームを悪用し、利用者を罠にはめる巧妙なサイバー攻撃です。
攻撃者は、SNSや掲示板など、誰もが気軽に書き込めるWebサイトに、悪意のあるスクリプト(プログラム)を仕込みます。まるでWebサイトに仕掛けられた「落とし穴」のようなもので、何も知らない利用者がそこに足を踏み入れると、さまざまな被害に遭う可能性があります。
例えば、攻撃者はメールやSNSを通じて、罠が仕掛けられたWebサイトへのリンクを送りつけるケースです。利用者がそのリンクをクリックすると、スクリプトが自動的に実行され、個人情報が盗まれたり、偽サイトに誘導されたりする危険性があります。
過去には、YouTubeのコメント欄に仕掛けられたXSSによって、多くのユーザーが被害に遭った事例もありました。コメントが消えたり、偽ニュースが表示されたり、全く関係のないサイトに飛ばされたりするなど、その被害は多岐にわたります。
バッファ・オーバーフロー
バッファオーバーフローは、プログラムがデータを処理する際に使用する「器」(バッファ)に、許容量を超えるデータを無理やり詰め込み、プログラムを混乱させ、悪意ある操作を可能にするサイバー攻撃です。
例えるなら、小さなコップに大量の水を注ぐと、水が溢れ出て周囲を濡らしてしまうように、バッファオーバーフローもプログラムの正常な動作を妨げ、予期せぬ事態を引き起こします。
攻撃者は、バッファオーバーフローを悪用し、プログラムを強制終了させたり、悪意のあるコードを送り込んだりして、システムを乗っ取ったり、機密情報を盗み出したりする可能性があります。
バッファオーバーフローは、システムの根幹を揺るがす深刻な脆弱性であり、対策は企業にとって喫緊の課題です。
セキュリティホールによる被害事例
セキュリティホールが原因となって発生した被害事例を3つ紹介します。具体的な事例を知ることで、セキュリティホールをより深く理解しましょう。
Windows OSのゼロデイ脆弱性
2014年、Windows OSでゼロデイ脆弱性が発見され「SCADA(産業制御システム)」をターゲットとしたサイバー攻撃が実施されました。この事例は諜報目的のサイバー攻撃で、ロシアのサイバー攻撃集団「Sandworm Team」が主導しました。
ウクライナやポーランドの産業制御システムがターゲットで、主な原因は「エアー・ギャップ」という手法を防御方法として展開していたためです。この手法は、デバイスとネットワークを物理的に切り離してセキュリティを確保するものです。
さらに、この事例ではシステムのアップデートに十分な注力がされておらず、セキュリティ環境が十分に構築されていなかったことも要因となりました。
macOS・iOSのゼロデイ脆弱性
2022年2月、アップル社はmacOSおよびiOSについて、緊急アップデートを発表しました。これは、WebブラウザSafariに搭載されているHTMLレンダリングエンジンWebKitで発覚したゼロデイ脆弱性への対応のためです。
この脆弱性が悪用されると、任意のコードを実行可能状態になります。緊急アップデートでは、カーネルでのローカル特権昇格、証明書の検証不備、およびWebKitにおける任意コード実行の問題の3つの脆弱性が修正されました。
この事例においては、アップル社のすばやい対応により、大きなトラブルに発展しませんでしたが、この事例は大手企業のソフトウェアであってもゼロデイ攻撃の対象となる可能性があることを示しています。
Zoomでの権限管理の脆弱性
2022年6月に大手オンライン会議ツールZoomにおいて、いくつもセキュリティホールがあることが発覚しました。この事例では、これらの脆弱性を悪用され、会議参加時に不要なプログラムがインストールされることで、任意のコード実行による被害が発生してしまったのです。
また、この事例では一部のバージョンで権限の管理が問題となり、主催者の同意を得ることなくオンライン会議に参加可能な状態になっていました。Zoomはすでにアップデートプログラムを提供し、これらのセキュリティホールを解決しています。
セキュリティホールへの対策方法
企業の情報を脅かすセキュリティホールは、重大な脅威です。そこで、セキュリティホールを狙った攻撃について、未然に防ぐための対策について紹介します。
セキュリティパッチを最新状態にする
セキュリティパッチとは、ソフトウェアやOSの脆弱性を修正するためのプログラムであり、例えるなら、病気から身を守るためのワクチンです。
サイバー攻撃者は、常に新たな攻撃手法を開発しており、セキュリティホールを発見し、それを悪用しようと狙っています。セキュリティパッチは、これらの攻撃からシステムを守るための重要な防御策です。
定期的にセキュリティパッチを適用すると、システムの免疫力を高め、サイバー攻撃に対する抵抗力を強化できます。ソフトウェアの自動更新機能を有効にするか、定期的に手動で更新を確認し、常に最新の状態を保つことが重要です。
セキュリティパッチを最新の状態に維持するのは、サイバー攻撃のリスクを最小限に抑え、安全なデジタル環境を維持するための基本的な対策と言えるでしょう。
脆弱性診断・ペネトレーションテストを実施する
ペネトレーションテストは、いわばセキュリティの「実地訓練」です。企業のシステムを守るホワイトハッカーが、実際にハッカーと同じ手法を用いてシステムへの侵入を試みます。
システムの「穴」を見つけ出し、現実的な攻撃シナリオを想定して、セキュリティ対策の有効性を検証することができます。
一方、脆弱性診断は、セキュリティの「健康診断」のようなものです。専門家や専用のツールを使って、システム全体をくまなくチェックし、潜在的な脆弱性を洗い出します。
開発者自身では見落としがちなセキュリティホールを客観的に評価し、適切な対策を講じるための指針を得られます。
どちらのテストも、企業のセキュリティレベルを向上させるための重要なものです。定期的に実施し、未知の脆弱性を早期に発見し、サイバー攻撃による被害を未然に防げます。
ペネトレーションテストと脆弱性診断は、企業のセキュリティ対策における「攻め」と「守り」の両面から、システムの安全性を確保するための強力なツールと言えるでしょう。
セキュリティ対策ソフトを導入する
サーバーへの攻撃を試みる攻撃者が増加しており、サーバーの適切な保護が求められています。OS向けのセキュリティ対策ソフトには、リアルタイム保護やネットワークを監視する機能などが搭載されており、企業の情報を守る上で非常に有効です。
セキュリティ対策ソフトは、常に最新の脅威情報を基に監視をおこない、異常な動きを迅速に検知する役割を果たします。
セキュリティ対策ソフトの主な機能として、リアルタイムでの監視・検知、ウイルスやマルウェアの隔離・削除、不正なWebサイトやフィッシングサイトの検知があります。
これらの機能を持つセキュリティ対策ソフトを導入して、常に動作させていると、セキュリティホールのリスクを長期的に軽減できます。
サポートが終了したソフトは利用しない
サーバーやネットワーク機器を動かすソフトウェアには、それぞれサポート期間が設定されています。ソフトウェアの開発元が、バグ修正やセキュリティパッチの提供などのサポートをおこなう期間のことです。
しかし、サポート期間が終了すると、たとえ新たな脆弱性が発見されても、修正プログラムが提供されなくなります。まるで家のセキュリティシステムが故障したまま放置されているようなもので、サイバー攻撃者にとって格好の標的となってしまうでしょう。
特に、社内で長年使用しているソフトウェアの場合、いつの間にかサポートが終了し、脆弱性が放置されているケースも少なくありません。
企業は、自社で利用しているソフトウェアのサポート期間を常に把握し、サポート終了前に新しいバージョンへの移行や代替ソフトウェアの導入を検討する必要があります。
サポート終了したソフトウェアを使い続けるのは、セキュリティリスクを高め、企業の貴重な情報資産を危険にさらすことにつながります。
定期的なソフトウェアの棚卸しをおこない、サポート期間を管理することは、企業のセキュリティ対策において非常に重要な取り組みと言えるでしょう。
WAFを導入する
WAF(Web Application Firewall)はWebアプリケーション層を保護するためのファイアウォールで、脆弱性のあるWebアプリケーションが被害に遭うリスクを軽減します。
WAFには通信監視・制御、Cookie保護、IPアドレス拒否、ログ・レポートなどの機能があり、不正なアクセスや攻撃に対して、ブロックする役割を果たしてくれます。WAFを導入すると、セキュリティホールへの攻撃に対して効果的な防御が可能です。
専門家へ依頼する
ノウハウのあるベンダーに依頼するのはひとつの方法です。企業を攻撃から守るためには、まずセキュリティホールを見つけることが必要ですが、これを専門家でない人がおこなうのは難しいのが現実です。
攻撃の方法は日々変化しているため、最新の情報を確認し、社内のセキュリティ対策に反映する必要があります。しかし、すべてを社内で対応するには、人材やコストなどのリソースに負荷がかかる場合もあるため、専門家に依頼すれば、効果的なセキュリティ対策を実現できます。
セキュリティホールの対策をしよう
本記事では、WebサイトやWebアプリケーションを狙うさまざまなサイバー攻撃とその脅威、そして具体的な対策について解説しました。
現代社会において、Webサイトは企業の顔であり、顧客との重要な接点です。しかし、その一方で、サイバー攻撃の格好の標的となっている現実もあります。
攻撃者は、Webサイトの脆弱性を巧みに利用し、情報漏洩やシステム破壊、さらには企業の評判失墜といった深刻な被害をもたらします。
ファイアウォールやセキュリティソフトの導入だけでは、もはや十分な防御とは言えません。多種多様なサイバー攻撃に対抗するためには、多層的なセキュリティ対策が必要です。
企業は、自社のWebサイトやシステムが常に攻撃の脅威にさらされていることを認識し、万全の対策が求められます。
セキュリティ対策は、決して「一度導入すれば終わり」ではありません。常に最新の脅威情報を把握し、対策をアップデートしていくことが重要です。
複数のセキュリティ対策を組み合わせ、総合的な防御体制を構築すれば、企業はサイバー攻撃の脅威から身を守り、安心して事業を展開できます。
コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング
コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。
クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由
②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供
③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス
クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。
無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
関連記事

サイバーセキュリティ
マクロウイルスとは?オフィス製品に感染する仕組みと対策を解説!
マクロウイルスは、ビジネスに不可欠な「マイクロソフトオフィス」製品のマクロ機能を悪用するマルウェアの一種です。ここでは、マクロウイルスの特徴と感染経路や、具体的な種類と被害例、詳しい対策方法について解説します。感染の仕組みを理解して対策を講じましょう。

サイバーセキュリティ
サイバー攻撃とは?攻撃の目的・種類や手口と被害事例から対策を紹介!
サイバー攻撃とは、サーバやパソコンなどの機器に対して不正アクセスや情報窃取、破壊活動などを行う攻撃の総称です。近年はサイバー攻撃が高度化し、どんな組織もサイバー攻撃にあうリスクがあります。本記事では、サイバー攻撃の種類や手口、被害事例について詳しく解説します。
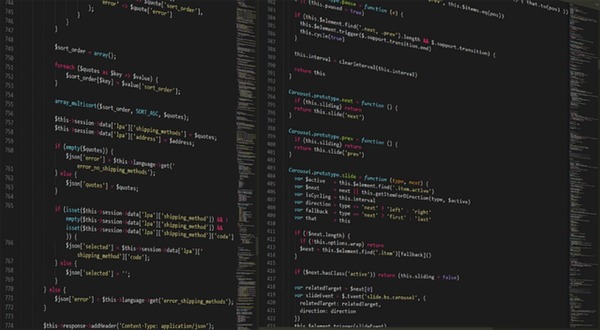
サイバーセキュリティ
VPNのセキュリティは安全?仕組みやメリットとリスクを解説!
本記事ではVPNのセキュリティについて解説しています。安全性と危険性、仕組み、メリット、さらにはリスクまで詳しく説明しています。最後まで読むと、VPNのセキュリティをよく理解できますので、企業のセキュリティ対策に役立ててください。

サイバーセキュリティ
ネットワークセキュリティとは?リスクと取るべき対策まとめ
本記事ではネットワークセキュリティについて解説しています。ネットワークセキュリティのリスクや事例、必要な対策を詳しく説明しています。企業に欠かせないセキュリティ対策がよく理解できますので、最後まで読んで参考にしてください。

サイバーセキュリティ
マルウェア対策とは?感染の脅威と対処法を事例や感染経路とともに解説!
この記事では、マルウェアの定義、脅威、感染経路、予防対策、感染後の対処法について解説しています。マルウェアはウイルス、トロイの木馬、スパイウェアなどを含み、個人情報の盗難やシステム破壊を目的としています。感染経路は多岐にわたり、予防にはソフトウェアの更新、セキュリティソフトの導入、不審なメールの回避などが必要です。感染後はネットワークの遮断とマルウェアの駆除、データの復旧などが重要です。

サイバーセキュリティ
身代金要求型ウイルス(ランサムウェア)の手口とは?データを守るための対策も紹介!
ランサムウェアとは身代金要求型のウイルスのことを指し、世界中で深刻な被害をもたらしています。その攻撃手口も巧妙化しており包括的なセキュリティ対策が求められます。この記事では、身代金要求型不正プログラムといわれるランサムウェアの概要、感染経路、手口や対策を詳しく説明します。

サイバーセキュリティ
ランサムウェアに感染したらどうする?感染経路と予防法や感染後の対処法を解説!
ランサムウェアの基礎知識と感染による被害、感染経路や予防策、感染したら行う対処法と禁止事項を具体的に解説します。ランサムウェアに感染したら被る金銭被害や業務停止、情報漏えいなどのリスクを回避するために必要なセキュリティ対策や教育など役立つ情報を提供します。

サイバーセキュリティ
マルウェアとランサムウェアの違いとは?特徴や感染経路と対策について解説!
ランサムウェアはマルウェアの一種であり、近年、ランサムウェアを含むマルウェアの被害が増加しています。企業や組織をマルウェアから守るためには、その特徴や対策を正しく理解することが重要です。 そこで本記事では、それぞれの違いや特徴、感染経路、対策を解説します。
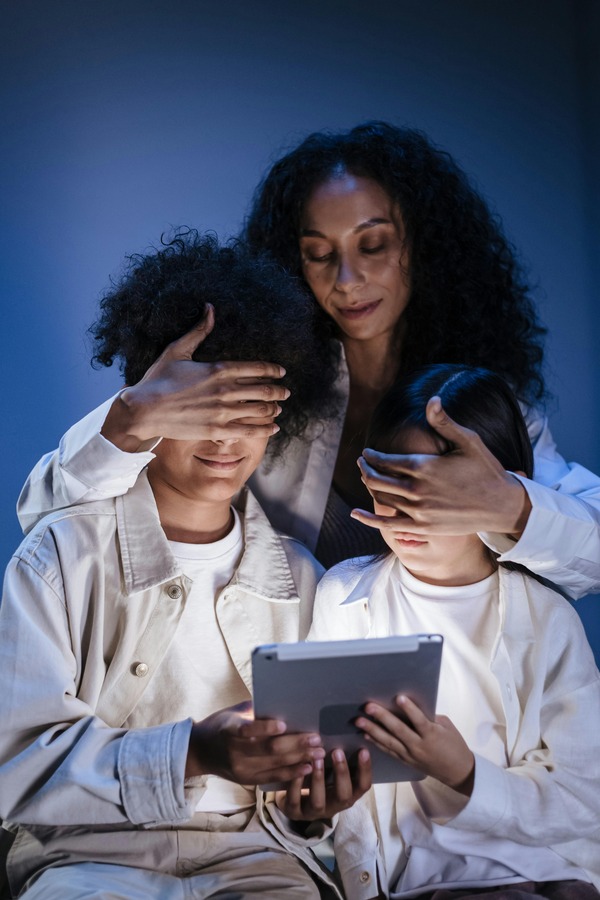
サイバーセキュリティ
ソーシャルエンジニアリングの手口とは?特徴や対策と被害事例を解説!
ソーシャルエンジニアリングとは、人間の心理的な隙を突くサイバー攻撃です。本記事ではソーシャルエンジニアリングの特徴や手口について解説します。実際に起きた事例も紹介するので、ソーシャルエンジニアリングの対策に役立ててください。
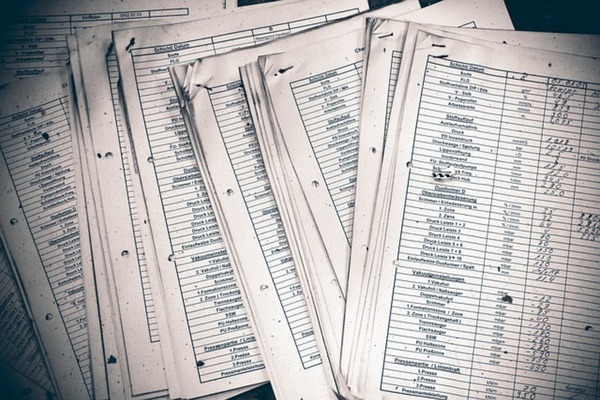
サイバーセキュリティ
ホワイトリストとは?対策の仕組みやセキュリティのメリットを解説!
ホワイトリストとは、安全と評価したWebサイトやIPアドレス等を定義したリストです。ホワイトリストに登録しているアプリケーションや通信のみ実行を許可します。ホワイトリストに登録していないものは全てブロックするため、高いレベルのセキュリティ対策となります。































